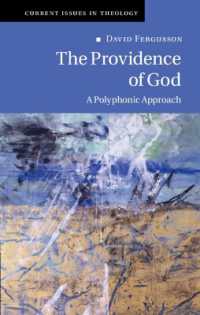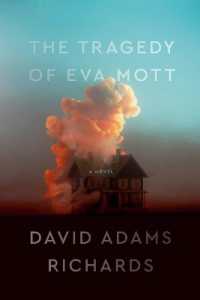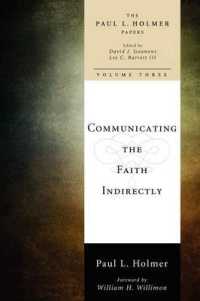内容説明
西洋中世における遍歴職人の「旅」とは、糧を得るための苦行であり、親方の呪縛から解放される喜びでもあった。彼らを迎える旅篭は常連客に優先してテーブルを割り当て、旅人を区分するしきたりを持っていた。遍歴職人・親方・旅篭主人達の必死なせめぎ合いに、当時の名もなき民衆の悲哀が漂う。本書は歴史の表舞台に登場しない彼ら庶民にスポットを当てた社会史。丹念な考察により、当時の人びとの息吹が蘇る。中世史研究の第一人者の初期代表作。’80年サントリー学芸賞受賞。
目次
1 道・川・橋
2 旅と定住の間に
3 定住者の世界
4 遍歴と定住の交わり
5 ジプシーと放浪者の世界
6 遍歴の世界
著者等紹介
阿部謹也[アベキンヤ]
1935年、東京に生まれる。1963年、一橋大学大学院社会学研究科博士課程修了。小樽商科大学教授、一橋大学教授、一橋大学学長、共立女子大学学長などを歴任。一橋大学名誉教授。2006年9月死去。『中世を旅する人びと』で’80年サントリー学芸賞を受賞した(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
こばまり
54
市井の人々は主役になりにくい為か、歴史ドラマなどでもつい風景の一部のように眺めていたのだが、思えば肉屋も羊飼いも水車番も渡し守も居酒屋の亭主も、皆何らかの立場を表し記号として存在してもいたのだと今更ながら気付かされた。長く読み継がれるのも納得。2021/02/08
Christena
15
中世ヨーロッパの庶民の暮らしについて書いた本。定住者と旅人、農民と羊飼い、パン屋や肉屋、職人とジプシー、放浪者など、それぞれの職業に携わる人の社会的地位や集団の関係などを解説していて、当時の人々の様子が生き生きと浮かびあがってくるように感じました。挿絵も綺麗です。2014/10/26
めぐ
12
記録にも残っていないような遠い昔の遠い国の人を少し身近にしてくれ、中世ドイツ語圏の面白いことも怖いことも生き生きと思い描かせてくれる本です。阿部謹也さんの本は何冊読んだか覚えていないけれど、当時の農村の雰囲気や景色、都市の空気感などを誰にでもほんのり見えるようにしてくれる優しくて知的な語り口が好きです。昔の人たちも自分と同じように人間だったんだ、と思えます。ティル・オイレンシュピーゲルを岩波赤で読んでみたいです。2018/02/28
Alm1111
11
阿部謹也、安定の中世庶民の歴史。庶民に寄せる阿部氏の視点が温かく、筆も走っている感。特にギルドやツンフトの精神が現在のドイツ人の根底に流れているという話は興味深い。個人的には終わりのオレインシュピーゲル論が、そこまで取り上げられていた中世を旅する人々とややテイストが違っていて、研究論比較のようで…確かに庶民の憂さ晴らしとして彼らの生の声ではあるのだけど。別の本でまとめてもよかったのではーと思った。2025/03/12
鮭
11
ドイツを中心とする中世欧州の生活史をまとめた一冊。 個人的には居酒屋の村における役割や街道の役割が興味深い。 RPGにおける村や宿屋の設定は決して根拠がないことではないことが、本書からもわかる。2019/06/22
-
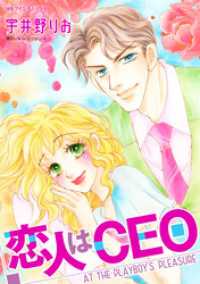
- 電子書籍
- 恋人はCEO ハーレクインコミックス