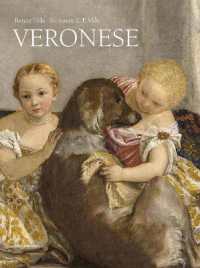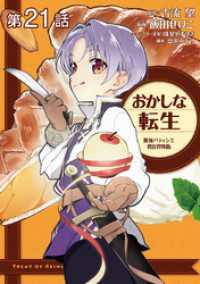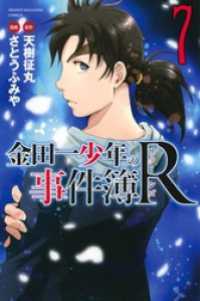内容説明
文政期の日本で、多くの門人を育て、医学の発展に大きな足跡を残したシーボルト。彼はまた、植物学に造詣の深い博物学者でもあった。日本の植物を初めてヨーロッパに紹介したシーボルトの『日本植物誌』は、植物学的にも、民俗学や文化史の観点からも、またボタニカルアート(植物画)としても、今も高く評価される貴重な資料である。そこには、当時シーボルト本人が目にしたさまざまな日本の植物の姿と特徴を描いた、美しい彩色図版150点が収められている。その全点を再現収録、日本の植物についてのシーボルトの覚書きや最新の研究知見を踏まえた書き下ろし解説を付す。
目次
シキミ
シイ
レンギョウ
オキナグサ
シュウメイギク(別名キブネギク)
ウツギ
マルバウツギ
ヒメウツギ
ツクシシャクナゲ
キリ〔
著者等紹介
シーボルト,P.F.B.フォン[シーボルト,P.F.B.フォン][Siebold,Philipp Franz Balthasar von]
1796‐1866年。ドイツ出身の医学者・博物学者。1823(文政6)年に、長崎のオランダ商館の医師として着任。日本の動植物・地理・歴史・言語などを研究。私塾「鳴滝塾」を開いて実地に診療しつつ医術を伝授した。29年離日
大場秀章[オオバヒデアキ]
1943年東京生まれ。東京大学名誉教授、同大学総合研究博物館特任研究員、植物多様性・文化研究室代表。理学博士。植物分類学専攻(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。