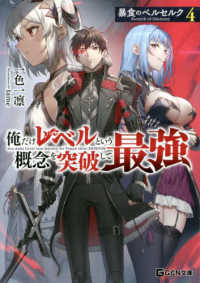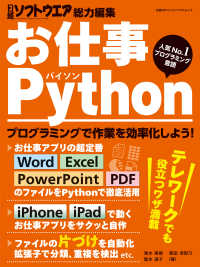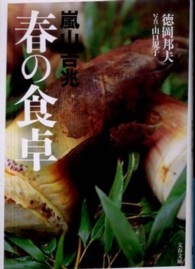内容説明
情報化や国際化が一段と進み、文化や文明が本質的な変貌をとげたかのように見える現代。この歴史の曲がり角で日本人は、どのように自らを表現し、生きていけばよいか。世の中の流れの中で立ち止まり、日本の歴史や伝統文化の諸相を見つめ直すところから始めてみよう。「鹿おどし」と「噴水」を比較して日本独自の時間や空間における志向を分析した「水の東西」、自らを正確に分析し適切な自己表現を得ることで真の国際化をめざす「鹿鳴館と神風連のあいだ」など、透徹した思考に支えられた文明批評・日本文化論。高校生にもぜひ読んでもらいたい一冊。
目次
第1章 日本の自己表現(自己イメージの分裂;十六世紀は実験室 ほか)
第2章 手とイメージ(情報化の歪み;変質する情報 ほか)
第3章 都市の復活のために
第4章 日本人の心とかたち(無常のリズム;水の東西 ほか)
第5章 曲り角で考える(「虚」の国に生きる覚悟;労働から仕事へ ほか)
著者等紹介
山崎正和[ヤマザキマサカズ]
1934年京都生まれ。京都大学文学部哲学科卒業。同大学院美学美術史学専攻博士課程修了。劇作家、評論家。関西大学教授、コロンビア大学客員教授、大阪大学教授、東亜大学学長を経て、現在、LCA大学院大学学長。中央教育審議会委員長として政策策定にも参画。文化功労者(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
i-miya
43
2011.02.17 (カバー裏) この時代、日本人はどう自らを表現したらいいのか。「水の東西」‐鹿おどしと噴水の比較、鹿鳴館と神風連の間にあるもの。(山崎正和) 1934、京都生まれ。京都大学哲学科卒。同大学院美学美術史専攻博士課程修了。関西大学教授。LCA大学院大学長。(あとがき) 1970年代もあと3年を残すばかり。(S52、淀河畔記す) (文庫へのあとがき) (2007.春)2011/02/19
楓
33
日本人と西洋人の価値観や感じ方の違いとして挙げられる例として、「鹿おどし」と「噴水」を山崎正和さんは挙げていた。その違いとしては①「流れる水」と「噴き上げる水」、②「時間的な水」と「空間的な水」、③「見えない水」と「目に見える水」、の以上3つの観点だ。3つのの観点から山崎さんが導き出した価値観の違いというのはとても興味深く、共感することができた。日本人は西洋人と違った独特の好みを持ってい、「行雲流水」という思想は思想以前に、積極的に、形なきものを恐れない心の現れにより裏付けられていた、という考えにも共感。2023/08/18
(*・ω・*)
3
高校の現代文の授業で習った「水の東西」が懐かしくなり手に取った。2016/02/28
Yuki
2
非常に楽しく読んだはずなのですが、いまいちどの評論も印象に残りませんでした。2018/12/08
壱萬参仟縁
2
江戸時代の文化政策は興味深い。現代日本の文化政策は、まちづくりの枠組みで語られることが多い。本章(040ページ~)は、江戸幕府は「いっさいの文化活動に公的な支持を与えることを止め、すべてを政治とは無縁の狭い『私』の世界へと追放してしまいました。(略)能楽だけは幕府の公認するものとなりましたが、(略)民衆とのつながりを持たないものにされてしまったのです」(043ページ)とある。これでは、主体をサポートする政策の意味がわからなくなる。鎖国時代の文化の実態を回顧して、現代の教訓にしておきたいものだ。2012/07/03