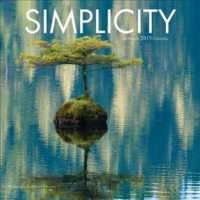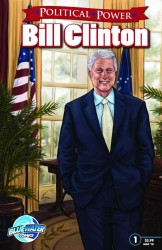内容説明
戦争は、一応の戦後処理が終わった後にも、その後の歴史に大きな、かつ持続的な影響を与えずにはおかない。しかも敗者の場合には、しばしば〈勝者=正義、敗者=悪〉という勝者による事後の正当化が加わるために、「戦後」の克服はいっそう難しい。私たちがまさに「戦犯裁判」や「靖国問題」などで体験しつつあるように、過去(=戦後)が現在を支配し続けているのである。ナポレオン戦争の敗者フランス、第一次大戦の敗者ドイツのそれぞれの戦後を、日本の場合と比較し、矛盾と混乱に満ちた「戦後」という特殊な時代を整除し「普遍化」する文明史の画期的な試み。
目次
プロローグ―戦後を評価する基準
第1部 ナポレオン戦争とその敗者フランスの戦後(ナポレオン戦争の新しさ;戦後処理の貴族的伝統;正統性の不在;堕落の開始=十九世紀)
第2部 第一次世界大戦とその敗者ドイツの戦後(大衆の欲した戦争;国家総力戦の破局;史上最悪の戦後?;ワイマール版・戦後の克服)
第3部 大東亜戦争とその敗者日本の戦後(正戦論の陥穽;日本の近代戦争の本質;共存か対決か;真珠湾とポツダムの間;第三の戦後=思想改造;勝者のジレンマと勝敗の収支決算)
著者等紹介
入江隆則[イリエタカノリ]
1935年生まれ。京都大学文学部、東京都立大学大学院(英文学)修了。岩波映画を経て明治大学教授となる。現在は明治大学名誉教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
筑紫の國造
9
「戦争論」ではなく、「敗戦後論」。クラウゼヴィッツの「戦争は他の手段をもってする政治である」という理論を基礎にして、フランス(ナポレオン戦後)、ドイツ(第一次大戦後)、そして日本(大東亜戦争後)の戦後を比較し、普遍化を試みる。もちろん、戦争そのものにも触れているが、主題となるのはあくまで「戦後」。貴族の戦いの名残があったナポレオン戦争と、古代征服戦争の様相を呈する第一次大戦後に対し、大東亜戦争後には何が起こったのか。ありそうでなかったテーマなので、戦後を巨視的に見るよい教科書になりそうだ。2017/02/07
p31xxx
1
本書は日本の戦後を類似点のあるナポレオン戦争後の仏、第一次大戦後の独の戦後と比較して論じ、普遍的な戦後論を目指したものである。クラウゼヴィッツの命題を根底として、政治の一手段としての役割から逸脱した戦争を、狂気に支配された戦争と位置付ける態度が一貫される。私が本書の中で最も気に入った事は、歴史上の悪者や英雄が矛盾と混乱の中で何を考えていたのかが示されている点である。また、平時はタブーとして語られることのない戦後を、このような形で正しく評価しようと試みることができるのは、直接経験のない私としてはありがたい。2011/05/19
朝吹龍一朗
1
前々から読みたかったのだがまとまった時間が取れずに敬遠していた書物。もっと早く取り掛かっておけばよかったと後悔した。 戦争とは他の手段を以ってする政治の継続である」というクラウゼヴィッツの命題から議論はスタートし、この立論を遠巻きにしながら進む。そしてその戦争の終わった後の時代の本質を描き出す。 「戦後とは「他の手段」で行われていた政治が、政治本来の手段に復帰した時代の謂であるから(中略)兵卒の血で購ってやっと手に入れた解決は、合理的なものではありえない」とし、ナポレオン戦争と第一次大戦のそれぞれの「2010/01/10
Naoya Tomihisa
0
✩✩クラウセヴィッツの戦争論にある「戦争とは、他の手段を以てする政治の実行である」を命題におき、近代の3つの大きな敗戦国を比較。戦後にも比較的上手く実行されたナポレオン戦争後のフランス、大衆主義に翻弄され多大なる賠償を求められた第一次大戦後のドイツ、その失敗を踏まえ思想的な支配を受けた太平洋戦後の日本。保守派バリバリの主張ながら、とても理論的なので、今こそぜひ左よりの人に読んで欲しい。2015/07/12
昼寝
0
太平洋戦争の敗者日本を、ナポレオン戦争の敗者フランスと第一次世界大戦の敗者ドイツと比較するという、壮大な戦争論。歴史上繰り返し戦争が起きたということは、それに合わせて「戦後」と「敗者」があったことを教えてくれる。2023/07/04