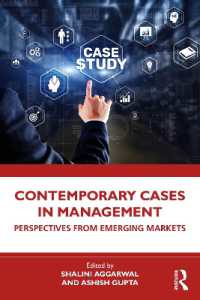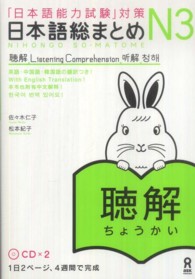内容説明
「色は匂へど 散りぬるを」「夏草や つはものどもが 夢の跡」―日本語の韻文の基本が、古来培われた七五調というのはご存じのとおり。五・七・五とくれば交通標語でもピシッと決まって聞こえる。しかし、声に出して心地よく耳にしっくりくるこの七五調の基盤には、ことばの切れ目と間から生まれる4拍子のリズムがあったのだ。日本人の内在律として生き続けてきたこのリズムを見つけ出し、「心地よさ」から日本語のアイデンティティーを探る、スリリングな日本語論。
目次
1 七五調はリズムか
2 七五調は四拍子
3 定型さまざま
4 英語俳句のおろかしさ
5 自由詩・散文のリズム
6 四拍子文化とその根元
著者等紹介
別宮貞徳[ベックサダノリ]
1927年東京生まれ。上智大学英文学科卒業。同大学院修士課程修了。元・上智大学文学部教授。翻訳家。幅広い知識を基に多岐にわたり活躍する(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
太田青磁
16
詩が詩であるためには、形式的には韻律が必要である・リズム=律動とは、読んで字のごとく規律正しい動きで、いいかえれば規則的なパターンのくりかえしである・つまり、五七五七七といいながら、時間的な長さにすれば八八八八八ということになる・歌と踊りと詩に共通の要素として、三者を結びつけているのはリズムである・「惜しくもあるかな」は字あまりには違いないが拍はあまっていないのに対し、「わが思う人は」は、字あまりであるのみならず、拍まであまっている・五音を四音、七音を六音にするには、確実に拍数が減るのである2018/04/20
サアベドラ
3
日本語のリズムは四拍で、五七五も実は四拍でできている、というおはなし。最後の方に出てくる「日本人は農耕民族だから四拍、朝鮮人は騎馬民族だから三拍」という説は正直うさんくさっと思ったけど、そこ以外はなかなか興味深い内容だった。2012/05/17
narmo
2
日本語のリズム?と、クエスチョンマークから読み始めましたが、面白かった!和歌短歌の句が同じ長さを構成しているという話はスルッと心に届きました。が、そのあとの三拍子辺りから???が浮かびっぱなしでしたが、最後の三段論法と因果の二極構造とスケールがぶっ飛んだところで心をぎゅっと掴まれました。根拠とか、もうどうでもいいわ(笑)、読後感はとにかく楽しいです。類似本(?)『粋の構造』九鬼周造箸かな。2018/07/29
BsBs
1
日本語を話す上において、発音していない部分、つまり読点や文節の区切りに着目してリズムを論じた画期的な本(実際にはちょっと先行研究があったらしい)。4拍子と拍は異なる概念だが、このことは日本の歌に三連符を使ったものがほとんどないことからも確認できる。一方主たる論でない部分は、はっきり言って胡乱な議論が繰り広げられており、西洋諸語や韓国語のリズム、農耕民族と騎馬民族のリズム(時期的にこのネタの出処はここ、人によってはデマって言ってたような)については、より慎重な議論が必要となる。全体的には奇書の類と思われる。2024/07/30
秋色の服(旧カットマン)
1
別宮先生。私は人生で2回お世話になりました。講義を聞いたわけでも、お会いしたわけでもないのに。英語が3拍子、日本語は4拍子。騎馬民族3拍子。大きなヒントになりました。ありがとうございました。2017/01/15