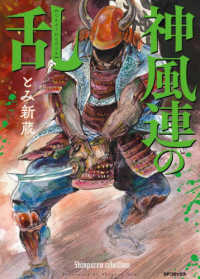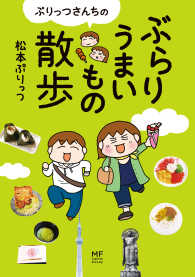内容説明
日本が農業中心社会だったというイメージはなぜ作られたのか。商工業者や芸能民はどうして賤視されるようになっていったのか。現代社会の祖型を形づくった、文明史的大転換期・中世。そこに新しい光をあて農村を中心とした均質な日本社会像に疑義を呈してきた著者が、貨幣経済、階級と差別、権力と信仰、女性の地位、多様な民族社会にたいする文字・資料の有りようなど、日本中世の真実とその多彩な横顔をいきいきと平明に語る。ロングセラーを続編とあわせて文庫化。
目次
日本の歴史をよみなおす(文字について;貨幣と商業・金融;畏怖と賤視;女性をめぐって;天皇と「日本」の国号)
続・日本の歴史をよみなおす(日本の社会は農業社会か;海からみた日本列島;荘園・公領の世界;悪党・海賊と商人・金融業者;日本の社会を考えなおす)
著者等紹介
網野善彦[アミノヨシヒコ]
1928-2004年。山梨県生まれ。東京大学文学部史学科卒業。名古屋大学助教授、神奈川大学短期大学教授、同大学特任教授を歴任。歴史家。専攻は、日本中世史、日本海民史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
はっせー
205
今まで学校で勉強してきた歴史は古代から現代まで年号ごとに区切られて勉強してきた。この本は年号ごとではなくジャンルごとに歴史を伝えている。また著者の網野さんが日本中世の専門家であるため中世を中心になっていた。南北朝の動乱によって今までの権力や特権が崩壊したことにより穢多 非人と呼ばれる人が出てきたのには驚いた。また百姓=農民というのが真実ではなかった。百姓とは我々一般市民を指しており、全員が全員農民ではないということが勉強になった。発売されてもう20年近く経つ。それでもなお輝き続けている本であった!2020/11/08
(haro-n)
122
再読読了。日本史を不勉強な人間の感想であることをご了承下さい。前半は、旧来の日本史の時代区分に疑問を投じ、14世紀の南北朝動乱を社会の大きな転換期としその社会変化の実態を明らかにする。以前は聖なる領域に関わる仕事をする存在として天皇や律令体制と結び付いて社会的地位も力も持っていた非人や遊女等は、律令体制の崩壊後の変化や彼らに対する「穢れ」の意識の強化を経て近世以降蔑視された。後半は、日本は農業中心の自給自足社会だったとするのは大きな間違いで、漁・林・商業などの多様な産業に支えられていたことを説明する。2017/07/10
おたま
94
網野善彦の本を読むのは初めて。一読、これまで持っていた「日本の歴史」に対するイメージが、様々な点で覆されていった。特に弥生時代以来農業が中心だと思っていた人々の暮らしが、実は百姓=農民ではなく、百姓の中には様々な業種の人、特に海上流通、金融、職人的な業種をしていたことも含まれるということに、常識的な見方が覆された。家の中に閉じ込められていた女性も、自由に出かけていく。「倭人」は、広く九州から朝鮮、中国沿岸部にも広がる地域だった。等々、そうとうイメージの転換が求められている。網野さんの他の本も読みたい。2021/12/14
kk
90
再読。『日本の歴史を読みなおす』を読みなおしてみました。前回読んだ際の記憶が殆ど飛んでしまっていて愕然としましたが、そのぶん新鮮な読心地。新たな気付き(?)を得られて感銘を受けました。農民が人口の大半だとされていた前近代社会像の虚実、14・15世紀以降における、資本主義的とも言える経済の発達、貨幣経済の萌芽期に宗教的なものが果たしたかもしれない役割、社会的差別の根源に向けた眼差しなど、我が国の伝統社会についての一般的なイメージに大きな波紋を呼ぶ、知的興味に溢れた問題提起の一冊です。2021/11/13
molysk
85
網野善彦は、歴史家。専攻は日本中世史。商工民、芸能民や海民などの非農業民に着目して独自の史観を構築した。本書は、日本社会の大転換期である中世を考え直す。前半は、古代における畏怖の対象が、賤視の対象へと変化する過程を、被差別身分や女性の地位、文字や貨幣、天皇の権威などから論ずる。後半では、農本社会と思われてきた日本が、実際には流通網や金融網が発達し、米以外の商品も交易された多彩な社会だったと述べる。穢れによる差別を受けながらも誇り高く生きる「道々の輩」を描いたのが、隆慶一郎の「吉原御免状」などの作品である。2020/02/11
-

- 電子書籍
- ヒロインポーズ_360° No.017…