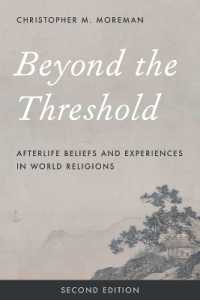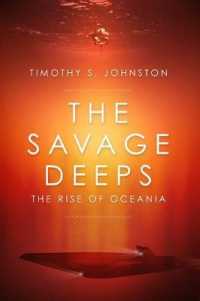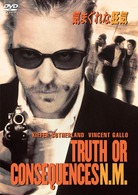内容説明
人間には、言語の背後にあって言語化されない知がある。「暗黙知」、それは人間の日常的な知覚・学習・行動を可能にするだけではない。暗黙知は生を更新し、知を更新する。それは創造性に溢れる科学的探求の源泉となり、新しい真実と倫理を探求するための原動力となる。隠された知のダイナミズム。潜在的可能性への投企。生きることがつねに新しい可能性に満ちているように、思考はつねに新しいポテンシャルに満ちている。暗黙知によって開かれる思考が、新しい社会と倫理を展望する。より高次の意味を志向する人間の隠された意志、そして社会への希望に貫かれた書。新訳。
目次
第1章 暗黙知
第2章 創発
第3章 探求者たちの社会
著者等紹介
ポランニー,マイケル[ポランニー,マイケル][Polanyi,Michael]
1891年、ブダペスト生まれ。ブダペスト大学で医学博士号・化学博士号取得。1933年、ナチスの人種迫害を避けて英国に亡命。マンチェスター大学物理化学教授(のち社会科学に転ずる)、オックスフォード大学主任研究員等を歴任。76年、死去
高橋勇夫[タカハシイサオ]
1953年岩手県生まれ。東京大学英文科卒。専修大学助教授
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
本屋のカガヤの本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
はっせー
94
かなり難しかった 暗黙知のメカニズムはなんとなく理解出来たが後半部分は本当に理解するのに時間がかかった。そのため暗黙知全体について理解することが出来なかった そのためこの本に出ていた参考文献を読みたいと思った!参考文献を読んだ後に再読したいと考えた2019/02/26
にいたけ
47
マイケル・ポランニーはノーベル賞も狙える物理化学者であったが哲学書のようなこの本を書いたのは何故かに興味を持った。物事を突き詰める西洋式の考え方に違和感を覚え、また、その考え方では幸せになれないと「グレー」な概念を作り出したのだと思う。物事を突き詰めればこうあるべきという考えに至る。SNSでその息苦しさを感じるものとしてはグレーな概念はストンと腹落ちした。2023/06/03
デビっちん
29
再読。「現行の知はいつまでたっても不完全なまま」この一言につきますね。めっさ刺さりました。何事も絶対化することはなく、今あることは次の段階の構成要素でしかなく、より上位の階層を志向し、更新し続ける必要があると。それは知という無生物だけが対象ではなく、人という存在も同じというところにハッとさせられました。深いなぁ。2018/03/24
zirou1984
27
暗黙知を簡単に言えば基本的に言語の外にある理解、語れなくとも自分の中に内在化されている知の事だが、より詳細には私たちが何かを知ろうとする時、既に内在化された知と関連付けられ、言語外のうちに包括的に統合されていくそのプロセスそのものだと言う事ができる。暗黙知そのものは包括的理解であり、それは分析し明示的統合を目指す科学的方法と相反するものだが、暗黙知がなければ科学的発展の為の問題設定が行えないのだという指摘はゼノンのパラドクスを克服する。未だ理解の途中だが興味深い論点が多数存在しており、議論されるべき名著。2013/06/13
りょうみや
24
読み友さんのおすすめ。哲学と認知科学の境界で哲学寄りの内容。原著は60年も前のものだけど現在の認知科学の理解に近い見解が読み取れる。暗黙知は身体的理解や無意識での学習に言い換えられる。ページ数は少ないのだけどなかなか骨のある内容。所々でこれまでのまとめと訳者解説があって助かる。2025/03/01