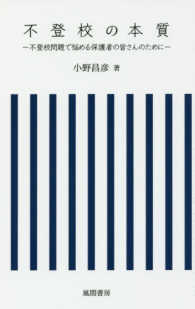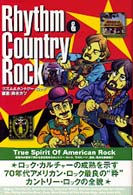内容説明
顔から群れへ、群れから群衆へ、そしてさらなる増殖へ…。群衆に抱かれながら、人々は触覚の喜びと恐れを覚え、その皮膚にあらゆる群れの感情を記憶させてきた。20世紀に登場した都市群衆という怪物は、新しい視覚体験を生む創像の源となるとともに、その一方、権力の繭となり所有と支配を産む力ともなる。創像者はやがて映像による知覚の革命を夢み、権力の繭からは〈監視者〉が姿を現わす。20世紀の群衆現象をたどり、精神科医クレランボー、エイゼンシュタイン、ヴィトゲンシュタイン、ウォーホルらの映像表現を渉猟しながら、群衆の管理のイメージの変遷を追う。
目次
襞のなかで眠りたい
サイケデリックス
なぜ顔に見えるのか
増殖の始まり
組み立て式の眼
階段から落ちる
ザンダー・エコロジー
家族的類似について
死の地勢学
エキストラはなぜカメラを見てはいけないのか
キングコング、クビライ・カン、カフカ?
人生と幸運
電子映像時代の芸術
群集―パリ・ベルリン・プラハ
注視者と測量士
著者等紹介
港千尋[ミナトチヒロ]
1960年生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業。ガセイ南米基金を受け、南米各地に滞在後、パリを拠点に評論家・写真家として活動を開始。現在、多摩美術大学助教授。著書に『記憶―「創造」と「想起」の力』(サントリー学芸賞)など
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
きつね
5
単行本版で読んだ。ほぼ毎頁に配された図版と、引用文献が幅広く、旅行者になった気分。ベンヤミンやウォーホルが引かれ、写真史の終わりに写真を考える為、後ろ歩きしながら写真の断片を積み上げていく趣。それが同時に群衆史(の終わり)でもある。本書には、視覚の制度は何を見なかったのか、写真は何を写さなかったのか?という問いが倍音として響き続けているように読める。本書冒頭の失明した精神科医クレランボーの自殺と、巻末のカント=アーレントのいう公平な注視者としての「盲目の詩人になること」との不気味な照応をこそ、凝視せよと。2013/08/22
子音はC 母音はA
0
哲学、人類学、精神分析の広範な知見と対象を思案させる為の色々な図版が鏤められた断章形式の一冊。(増殖の始まり)から(組み立て式の眼)の項目の流れが刺激に富んでいた。19世紀から20世紀にかけて群衆に対するデザインが単層的表現から複層的表現に変容していく様が興味深い。2013/10/04
-
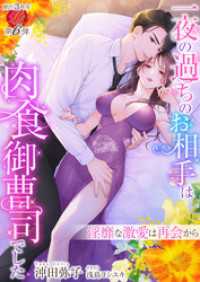
- 電子書籍
- 一夜の過ちのお相手は肉食御曹司でした …
-

- 和書
- ベーシック地理