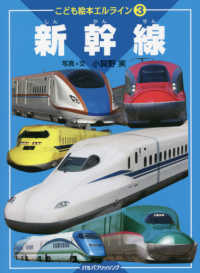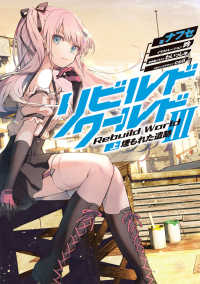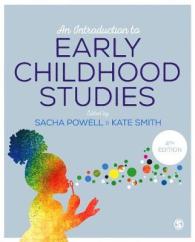感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
roughfractus02
8
極限や収束を用いて還元主義に陥らないような相補的プロセスに客観性を見出していく解析学的手順と、否定辞の厳密な表現の使用に基づき、アインシュタイン以後の「新科学精神」が、単なる排除としての否定でなく(不や反でなく、相補的な非としての非ユークリッド幾何学、非ニュートン的力学、非デカルト的認識論)、仮説と実験と推論の試行錯誤によって理論の限界を指摘しつつ補完し拡張を続ける運動のプロセスと著者は理解する。本書でこの過程における客観性は「客観的凝集」と呼び、技術や観察者の認識も含めた微細構造の変化として扱われる。2024/10/27
ポカホンタス
3
ユークリッド幾何学が無意識的に排除していた領域に光を当てたのが非ユークリッド幾何学だった。ニュートン力学から非ニュートン力学が生まれたのも同じ。物質とエネルギー、波動と粒子、いずれも相補的存在。実在と非実在とが複雑に入れ替わる世界を相対性理論はとらえ、決定論が見なかったものに光が当たった。デカルト主義はすでに陳腐でしかない。経験的世界のバイアスを超える科学と経験的世界に住む人間との弁証法こそが新しい科学的精神。中学高校で物理化学の教師をしていた著者らしく、科学を教育という視点で論じている点も興味深い。2019/03/05
ウオオオオオ
1
西郷・田口『〈現実〉とは何か』と共通した考え方が見られ、おもしろい。2020/05/05
Bevel
1
「首尾一貫性」という関係の合理的な側面があり、それが進むにつれて、関係の「客観的凝集」という実在的な側面が現れるようになる。とはいえ、「客観的凝集」は素朴な実在ではなく技術的プロセスの中にある微細構造とされる。この凝集は、いわゆる「非」としてはたらき、われわれの思考を促す側面をもち、あるときには理論的な革命のモチベーションというか契機にもなる。「凝集」が重なり合うことで、対象が人間の認識に与える衝撃が大きくなっていくというイメージが面白かった。2018/11/07
とある科学者
1
著者は、コントの科学哲学・科学史の流れを母国仏で汲む科学認識論学派の代表であり、又、世界的に哲学が論理学ネタになった時代にあっていかにも伝統の解析学王国の仏人らしく、解析学とその物理学的応用ネタが中心の哲学者。そんな著者が提唱する哲学の基礎が一通り学べる入門書が、本書。 難を言えば、初心者にはおそらく難しく、逆に数学的説明が平明過ぎて玄人には物足りず、少々中途半端な印象。同国のカルタン、ボレル、ルベーグら解析学者との哲学的共通点等をもう少し語って欲しいところ。しかし、代表作を補う参考書としての価値は高い。
-

- 電子書籍
- 妊娠したら夫が浮気しやがった ~デキサ…