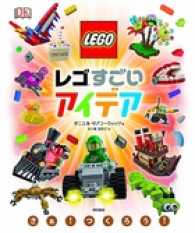内容説明
近代日本の宿命、西欧との交わりのなかで、その思想・文化の単なる知的理解ではなく、自己の内面から西欧を血肉化し、それに対応した日本認識を自らの命題とし、日々の生活を通して西欧という現実に食い入りながら思想経験にまで高めた森有正。この前人未踏の、きびしく逞しい、豊かな展望を内に含んだ精神的営為の真髄を全5巻に集大成。第5巻は、“経験”の深まりが“変貌”をみせて、著者の思想の到達点を示す『木々は光を浴びて』全篇と、さまざまな時期に日本を論じたエッセー5篇に、1970年から76年までの日記を収録。
目次
木々は光を浴びて(雑木林の中の反省;木々は光を浴びて、…;暗く広い流れ ほか)
故国の情感
東京の一隅
八月十五日の感想
現下の時点にあたって思う
三十年という歳月
日記(1970年1月25日~1976年8月6日)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ほーりー
1
社会の中に個人があることは一見疑い得ない事実のようでありながら、実際には、切実な経験は個人の中に社会があるという形でなされる。日本語を使った人間関係が既成の社会秩序を基礎に二人称で構成されて、三人称の第三者と一人称の個人の水平的関係はどこまでいっても存在しないという筆者の洞察を踏まえるならば、日本で個人を社会的に生かすことは極めて困難に思える。手がかりは、「二項方式は一・三方式と触れると必ず崩壊し」その時「主体の生き方が『変貌』する」ことにあり、これは第三者からすれば「沈黙して見守る外はない」問題だという2015/08/23