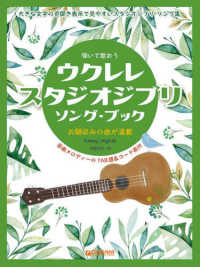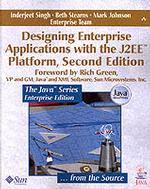内容説明
1927年に刊行されるや、ドイツの哲学界に深刻な衝撃をもたらした、ハイデッガーの最初の主著。《存在》の諸相をその統一的意味へさかのぼって解明すること、そして、存在者の《存在》を人間存在(=「現存在」)の根本的意味としての《時間》性から解釈することを主旨として、「現存在の準備的な基礎分析」と「現存在と時間性」の二編から構成する。上巻ではこの前者を収録した。「現存在」の根本的な構成が「世界=内=存在」として提示され、「現存在」のうちに見いだされる「存在了解」を探求すべく、基礎的な問いが差し出される。
目次
序論 存在の意味への問いの提示(存在の問いの必然性、構造および優位;存在問題の開発における二重の課題 考究の方法および構図)
第1編 現存在の準備的な基礎分析(現存在の準備的分析の課題の提示;現存在の根本的構成としての世界=内=存在一般;世界の世界性;共同存在と自己存在としての世界=内=存在、「世間」;内=存在そのもの;現存在の存在としての関心)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
さきん
34
存在と時間という題だが、時間について論ずるに至らず。しかし、デカルトのわれ思う故に我在りを前提とした今までの哲学を超えて、「在り」とは何かということ自体へ挑戦した。命題としては、人間がこれが「存在」と規定できる明確な定義ができるのかということなのが、結論から言えばないという読解。存在という概念は人間がものの上位概念として見出し、しかも「無い」という概念の反対にあたる。加えて、過去からの繋がりや石の塊をハンマーとして見出すような関係の中で存在は自在変化する。緑茶を見て、日本人の多くは緑茶で湯呑で飲むものだ2021/10/14
wadaya
15
存在という概念を定義することはできない。だからこそ、それを問う。存在を問う問いに答えが無いからこそ反復して問う。それがハイデガーの哲学的姿勢であり、共感できる。そしてそこに「循環」を含まないとするところも好きである。ハイデガーは人間がまさに存在することを「現存在」と呼んだ。それはデカルトのように「そこにある」だけではなく、その存在自身が、その存在を理解しているという意味である。そしてもう一つ、現存在が関わる存在自体を「実存」と呼んでいる。つまり、実存には現存在が必要だということである。我々人間は現存在で→2021/05/31
hitotoseno
13
変な本だ。通常、名著と称される書物は我々のような凡人からは遠く隔たった場所に存在している。もちろん、人間が記すものなのだからよくよく見ると人間味の抜けない瑕疵がないわけではない。そこから我々は少なからず馴染みを覚え、エライ先生も所詮はこんなものか、と侮りつつ、それにしても同じ人間がここまでの高みに達せられるものか、と回帰的に偉大さを確認する……しかし、『存在と時間』はそうした典型にあてはまらない。これは徹底的に卑俗な書物である。2016/05/31
K
11
ひとまず読み切ったけど、まあ、読みながら考えることは結構あって読みがいのある本だとは思う。デカルト、カント、フッサールを経ての、ハイデガーという立ち位置で読むとよいかもしれない。サルトルを読んでいると、ハイデガーの考えもしばしば出てくるので、そこの関係をみるのも面白い。あとはやっぱり、日本語だけでは全然ダメで、今回は少しは原文も参照したけど、重要なとこだけでも、通して読みたい。そのうち戻ってくるとして、一回研究書を何冊か読んでいま自分が得た解釈とすり合わしていきたい。2022/08/05
Gokkey
11
一度読んだだけですべての内容がストンと落ちるはずもないのだが、それでも木田元氏らの著作を事前に読んでいたおかげで何とか喰らいつくことが出来た。理解が上手く進まない箇所は追々岩波文庫版を参照する予定。言葉の16分音符の羅列ともいうべき怒涛の展開で読者の頭のスペースに一切の余白を残さずに世界内存在という構造を作り上げ、この構造を通して日常性や真理を解体してゆく。そう、上巻はこの構造(空間)の話だけなのだ。下巻はこのX-Y軸に対して時間というZ軸が加わるようだ。理解の鍵は世界内存在を中心としたトポロジーにあり。2020/03/11
-
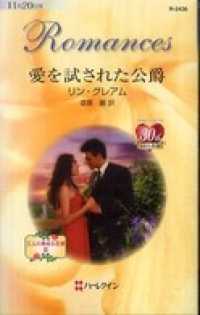
- 電子書籍
- 愛を試された公爵 三人の無垢な花嫁 I…