内容説明
人間にとって空間とは何か?それはどんな経験なのだろうか?また我々は場所にどのような特別の意味を与え、どのようにして空間と場所を組織だてていくのだろうか?幼児の身体から建築・都市にいたる空間の諸相を経験というキータームによって一貫して探究した本書は、空間と場所を考えるための必読図書である。
目次
序論
経験のパースペクティブ
空間・場所・子供
身体・人間関係・空間の価値
広がりと密集
空間の能力・空間の知識・場所
神話的な空間と場所
建築的な空間と認識
経験的空間のなかの時間
場所の親密な経験
母国への愛着
可視性―場所の創造
時間と場所
エピローグ
著者等紹介
トゥアン,イーフー[トゥアン,イーフー][Tuan,Yi‐Fu]
1930年中国で生まれる。中国系アメリカ人。オックスフォード大学で修士号、カリフォルニア大学バークレー校で博士号取得。ウィスコンシン大学マディソン校教授。70年代に現象学的地理学の旗手として颯爽と登場し、今日では、世界的な第一人者として知られている
山本浩[ヤマモトヒロシ]
1946年生まれ。上智大学文学部英文学科博士課程修了。上智大学文学部教授。イギリス演劇専攻(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ハチアカデミー
16
人間の空間認識から、記憶・モニュメント・神話などが付与されることで特定の感情を抱く場所へと変化する心性を探る一冊。場所とは、単なる数字や資産価値などで言い表すことができるものではなく、そこにはある種の感情、情緒が伴うものである。人は身体を持つ。その身体が向く方向が前となり逆が後ろとなり、左右、上下という認識が始まる。それは個別の感覚であり、その場限りの認識であるのだが、そこに文化や共通の記号が付されることで、共同体の共通認識となる。個別の経験が造る場所が、どのように共同幻想となるのかまで射程の広がる一冊。2014/06/10
ぱぴ
2
存在するという事実だけで生まれる「空間」という現象を、人はその一生でどのように認識して創造し、無意識の内に共有しているのか。人文科学の見地から研究された優れた一冊。著者が「入門書」という通り、全体的に広く、そこまで深入りせずといった内容なので、興味が多岐に広がっていく。人間は五感を使って物事を把握し、表現されにくいにおいや音などでも理解しているので、言葉で表すよりも非常に多くのことを知っているというところでは、ポラニーの「暗黙知の次元」に通ずるなと思った。2023/05/12
いたま
2
空間の現象学的な経験をテーマに、子供の身体的始原的な空間経験から、それを拡大した都市的経験にいたるまでを論じる名著。さながらケヴィン・リンチの『都市のイメージ』を継承するような内容だが、明らかに著者の視点は人文学的なものであり、文学的なテキストや人類学などの豊富な資料を引いている。人間にとって空間の経験とは極めて基本的なものであるが(生きることは空間にあることだ)それは豊かに文化的に影響されている。方角の感覚やそれに付随する価値判断等、著者は様々な「空間の経験」を探る。場所論的なテキスト研究の必読書だ。2021/05/28
GIGI
1
「人が抱く望みというのは、文化によって条件付けられている」然り。前提となる「条件」変化を求めて活動しているのかもしれない。自身への変革を求めて。「変化」を外に求めるのも内に求めるのも同義とするならば、「空間」はここにもある。空間の経験は、今の自分が得られる「望み」と条件付けが異なる作者の「望み」とでは決して交わらない「経験」かもしれない。他が知り得る「経験」と己が知り得る「経験」。生きることはこの「経験」をメタ認知するための条件付けかもしれない。2024/06/01
Kindman
1
実に分かりやすく、楽しい本だった。2019/06/16
-
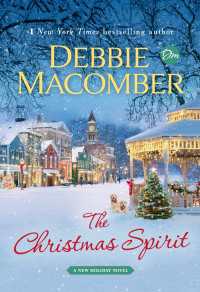
- 洋書電子書籍
- The Christmas Spiri…






