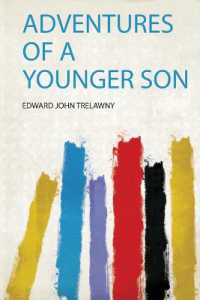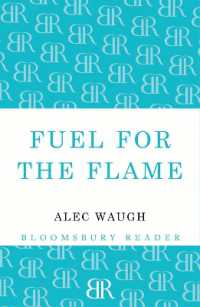内容説明
1888年、ニーチェを精神錯乱が襲う直前に、彼はその悲劇を予感するかのように、精力的に著作活動に従事する。ヴァーグナーとその運動への宣戦布告の書『ヴァーグナーの場合』『ニーチェ対ヴァーグナー』。そして、すべての価値の価値転換の書『偶像の黄昏』『反キリスト者』。キリスト教においては、生を強化するものが悪とされ、弱化するものが善とされる。すなわち、それは、強者に対する弱者のルサンチマンの所産にほかならない。ニーチェ最晩年の激烈の思索。
目次
偶像の黄昏
反キリスト者
ヴァーグナーの場合
ニーチェ対ヴァーグナー
附録(キリスト教に関する初期遺稿断片;リヒアルト・ヴァーグナーに関する諸相;『ヴァーグナーの場合』のための最初の覚え書;『ヴァーグナーの場合』のための別の準備草稿)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
しんすけ
22
最近は人間不信になることが、あまりも多すぎる。今に始まったことではないが、最近は増えるばかりの感に陥っている。マスクをしないで表に出ると殺気を感じる。ぼく以外の人間がすべて狂人になったのだろう。コロナ禍は人類終焉の証に過ぎないのに。コロナ禍は人類への警鐘なのだ。 黙して見過ごすことができないのか。 この状況においてニーチェの狂気に接すると安堵する。特に『反キリスト者(アンチクリスト)』において。 これは二―チェの狂気が語らしめたものであろう。 だが近代以後の世界は狂気を持たずしては描き切れないものだった。2022/06/02
∃.狂茶党
16
これまでで、一番わかり易いニーチェ。 『ツァラトゥストラ』とかは、ハイになってんだろうか。 民族主義とオカルトを結ぶ重要なキーワードが出てきて、文脈とは別に興奮。 ニーチェが民族主義かといえば、違うような気がするが、ナチズムなどに利用されやすいのも事実。 フランスに対する屈折した感情と、イギリスに対する見下し。 こう言った反応するのは、気になって仕方がないから。 2025/12/19
またの名
9
とりわけニーチェが猛烈に批判したキリスト教とワーグナーが主題の文章ばかりを収録しているので、彼一流の憎悪表現まがいの罵倒がますます絶好調。真の強者の復権を企む哲学者にとって、弱者の側に立つ教会の教義や道徳が人々を支配し権力を握るために捏造された虚構でしかないことは、気分が悪くなる自明の事実だった。神も目的も意志も真理も理性も善悪も因果関係も拒絶した超人の視点からは陶酔、性的興奮、欲情、快感が芸術の原理だと洞察できるのに、それを解していたはずのワーグナーが救済・宗教・大衆を求め始めた時に断絶は決定的になる。2015/11/30
松本直哉
7
再読。喧嘩を売られても買わない、法廷でのイエス。どんなに挑発されても、嘲弄されても、唾を吐きかけられても、沈黙をまもりとおす。「逆説的反抗者」と田川建三はイエスを呼んだが、沈黙こそは窮極の反抗。「反キリスト」という表題にもかかわらず、実際は「反キリスト教会」であり、個人としてのイエスに、ニーチェはひそかな共感を示す。
いいほんさがそ@蔵書の再整理中【0.00%完了】
4
**哲学**哲学ネタSF読解の為読了。西洋の精神的な価値感の一大転換を願ったニーチェにとって、キリスト教とは西洋の基盤そのものだった。しかし、牧師の家庭で生を受けた彼の心境は世間が思う程単純ではなかった―― 「反キリスト者」とは聖人ヨハネの言葉です。しかし彼はどのキリスト教に反したかったのだろうか・・・。キリスト教にしても初期キリスト教である"グノーシス"から様々な利害関係を経て形態変化を繰り返してきた。私は彼の神に対する言及から、むしろ組織腐敗を起こす前の超初期キリスト教を愛していたと思えてならない。2012/07/27
-

- DVD
- 戦争は終った