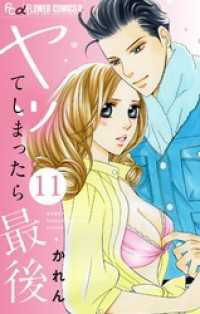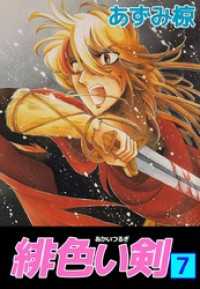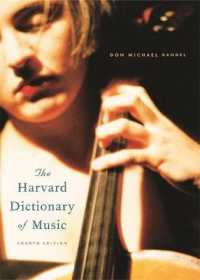出版社内容情報
生きてさえいければ貧困ではないのか? 気鋭の貧困理論研究者が、時代ごとに変わる「貧困」という概念をめぐる問題点を整理し、かみ合わない議論に一石を投じる
内容説明
貧困とは「お金がないこと」だと思っている人は多い。では生きていくための最低限のお金さえあれば貧困ではないのか?貧困の定義は実は時代ごとに課題にぶつかり、形を変えてきた。貧困層を劣った人間と見なす優生思想、男女差別を前提とした家族主義、子どもを救うに値する/しないに選別する投資の論理、貧困を努力の問題に還元する自己責任論…。気鋭の研究者が、「貧困」概念をめぐる議論と問題点を整理し、「貧困」が今もなくならないのはなぜかという根本的な問いに対峙する。
目次
序章 貧困とは何か?
第1章 生きていければ「貧困」じゃない?―絶対的貧困理論
第2章 家族主義を乗り越えるために―相対的貧困理論
第3章 ベーシック・サービス、コモン、社会的共通資本―社会的排除理論
第4章 「子どもの貧困」に潜む罠―「投資」と「選別」を批判する
第5章 「貧困」は自分のせいなのか?―「階級」から問い直す
終章 貧困のない社会はあり得るか?
著者等紹介
志賀信夫[シガノブオ]
宮崎県日向市出身。大分大学福祉健康科学部准教授。一橋大学大学院社会学研究科博士後期課程修了、博士(社会学)。NPO法人「結い」理事。専門は、貧困理論、社会政策。「貧困とは何か」について研究し、「いのちのとりで裁判」において意見書を執筆、大阪地裁、岡山地裁に有識者証人として出廷(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
- 評価
購入済の本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
けんとまん1007
山口透析鉄
よっち
sayan
kayak-gohan