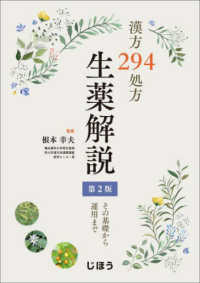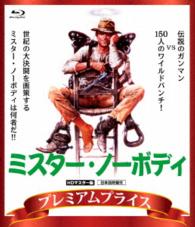出版社内容情報
「場面を描く、生活を書く」『タイミングの社会学』(紀伊國屋じんぶん大賞2024第2位)の著者、最新刊。エスノグラフィの息遣いを体感する入門書。
内容説明
生活を書く、それがエスノグラフィの特徴です。そして、もっとも良質なエスノグラフィの成果は、苦しみとともに生きる人びとが直面している世界を表し出すところに宿るものです。もともと人類学で発展したこの手法は、シカゴ学派を拠点に、社会学の分野でも広がっていきました。本書では、5つのキーワードに沿って、そのおもしろさを解説していきます。予備知識はいりません。ぜひ、その魅力を体感してください。
目次
第1章 エスノグラフィを体感する
第2章 フィールドに学ぶ
第3章 生活を書く
第4章 時間に参与する
第5章 対比的に読む
第6章 事例を通して説明する
著者等紹介
石岡丈昇[イシオカトモノリ]
1977年、岡山市生まれ。専門は社会学/身体文化論。日本大学文理学部社会学科教授。フィリピン・マニラを主な事例地として、社会学/身体文化論の研究をおこなう。著作に『タイミングの社会学―ディテールを書くエスノグラフィー』(青土社、2023年、紀伊國屋じんぶん大賞2024第2位)、『ローカルボクサーと貧困世界―マニラのボクシングジムにみる身体文化』(世界思想社、2012年、第12回日本社会学会奨励賞。2024年に増補新版)など(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
本屋のカガヤの本棚
-

- 洋書電子書籍
-
言語・社会・権力入門(第6版)
…