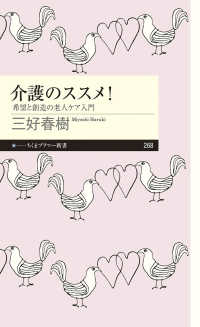出版社内容情報
伝統的な日本人のこころのあり方や死生観はどのようなものだったのか。民俗学や宗教学、倫理学の観点から、近代以降、我々が見失ってきたものを掘り起こす。
内容説明
現代の私たちは日本の伝統文化をあまりにも知らない。それは明治時代に西洋の知識や技術を取り入れるためにつくられた学校教育や近代の学問が、日本の文学や歴史を私たちの心から切り離して論じてきたからだ。伝統的な日本人の心のあり方や死生観はどのようなものだったのか。いま私たちが伝統的と思っているものの多くが、いかにして明治に入ってからつくりだされてきたのか。民俗学や宗教学、倫理学等の観点から近代以降に日本人が見誤り、見失ってきたものを掘り起こす。
目次
序章 日本人の知らない日本の伝統
第1章 神のまつりと日本人(民俗学が目指したもの;柳田国男と折口信夫―二人の関心の違い)
第2章 仏教と日本―古代から中世へ(仏教の伝来と展開;神仏習合と中世の文化)
第3章 新しい知の到来―近世・近代(中世から近世への転換;明治維新から現代にいたるまで)
著者等紹介
吉村均[ヨシムラヒトシ]
1961年東京生まれ。東京大学文学部卒業。東京大学大学院人文科学研究科博士課程修了。日本学術振興会特別研究員(DC)を経て、現在、公益財団法人中村元東方研究所専任研究員。横浜市立大学・東洋大学・明治学院大学・東京女子大学非常勤講師。専門は日本倫理思想史、仏教学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
tamami
50
題名にある「日本の伝統文化」というのはやや大風呂敷で、帯に書かれた「私たちの心はどこから来たのか?」ー民俗学、宗教学、倫理学から探る起源と展開ーというのが、的確なところか。古代の神まつりから、神仏習合、近世近代における儒教・キリスト教などの受容まで、日々の生活で実感する宗教的行事や意識の変遷を詳述する。伝統行事の中には、明治以降に政策として形作られたものも少なくないとの指摘があるが、人々にもそれらを受け入れる素地もあったのではないかと思う。またその多くが、わが国の風土に根ざした物であることに安心を覚える。2023/12/27
Mihoko
4
えー!そうなんだ!ととても良い内容なのだけれど、あまりにも知識のない私には理解できない箇所あり。折口信夫氏や柳田国男氏の名は知ってるし、和辻哲郎氏の「風土」を昔読んだよ。民俗学に触れたくなる書籍。 2024/05/26
srmz
2
日本の伝統文化、奥が深い! 馴染みがない言葉が多いからか難しく感じる🫠 けど1冊1000円もしない金額で 大学の講義内容がギュッと詰まっているものを 本で学べるって改めてすごい🙄✨ 本書では、特に仏教、民俗学、宗教学、倫理学などを縦断する視点で、 日本人の精神性や死生観、自然観を掘り下げている。 ただ、仏教要素や柳田国男・折口信夫らの論点が多く登場するため、 「偏り」を感じる部分もあるかもしれない☹️ また、単なる「知識」ではなく、 自分自身の生き方や感性を省みるヒントになった💡2025/10/08
ひつじパパ
2
中国から入ってきた仏教が、神話や物語などにも混じって、鎌倉仏教などの諸々から日本人の生活に影響を与えていくという流れをみれた。柳田國男と和辻哲郎のそれらの民俗を、まとめ、思想としてだした論は、自分には難しくてわからなかった。2023/12/14
taq
1
日本の伝統、といっても明治維新以降に作られたものが多い中、現在の日本人の深層を形成している古来の文化について、民俗学や仏教という視点から光を当てる。寺と神社が渾然一体となっていた明治以前は、「神」といっても今の神社で祀られている神々とは全く違ったものだったということで(八幡大菩薩など)、実際にその時代の信仰を見てみたかったと切に思う。大学の一般教養に当たる講義をまとめたものなので読みやすいが、特に明治以降の記述は簡略化されすぎており、もう少し突っ込んで知りたいと感じた。2024/05/22
-
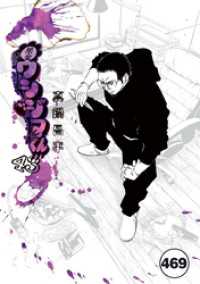
- 電子書籍
- 闇金ウシジマくん【タテカラー】 ウシジ…
-
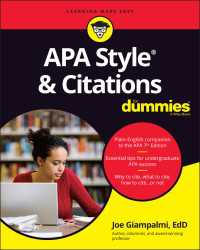
- 洋書電子書籍
- 誰でもわかるAPAスタイル・引用作法<…