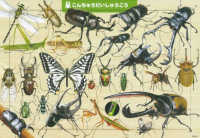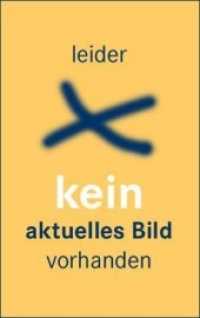出版社内容情報
文字、木簡などの記録メディア、年号などの興りとは。古代中国人の歴史記述への執念、歴史観の萌芽。それらが司馬遷『史記』へと結実する。歴史の誕生をたどる。
内容説明
現代にも通じる歴史書と評価される司馬遷『史記』だが、執筆には、それより前に記録され、伝えられたものの蓄積がある。当然のことながら、文字がなくてはならないし、竹簡などの記録メディアが必要。さらに、それがいつの出来事かを記述するためには、国王の治世や暦等を根拠にした年号もあるほうがいい。正史は権力者の歴史認識と思想を汲むため編者は命懸けだが、すでに古代中国においても過去の事象からいまの問題を見出す態度の萌芽が見られる。出土史料を繙きながら、『史記』に結実する記録への執念や歴史観の興りをたどる。
目次
序章 記録のはじまり―殷代
第1部 歴史認識(同時代史料から見る―西周~春秋時代1;後代の文献から見る―西周~春秋時代2)
第2部 歴史書と歴史観(歴史書と歴史観の登場―戦国時代;そして『史記』へ―秦~前漢時代)
終章 大事紀年から年号へ
著者等紹介
佐藤信弥[サトウシンヤ]
1976年兵庫県生まれ。関西学院大学大学院文学研究科博士課程後期課程単位取得満期退学、関西学院大学博士(歴史学)、専攻は中国殷周史。立命館大学白川静記念東洋文字文化研究所客員研究員および大阪公立大学客員研究員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 和書
- 続々・秋田学入門