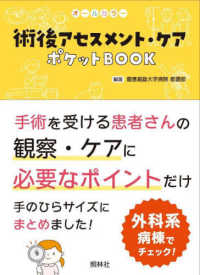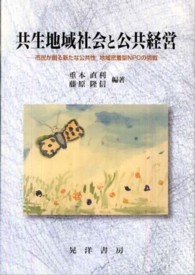内容説明
旧石器ねつ造事件で、考古学は変わったのか。弥生時代は、さらに500年も早く始まっていた?信長・秀吉の城も、長崎の出島も、考古学!?調査・発掘にまつわる知られざる実態から、年単位で年代を推定する最新の測定法まで、考古学の「今」を、手軽に知り尽くす。
目次
第1講 発掘調査とは?「考古学」という学問は?
第2講 旧石器文化研究の現状は?
第3講 世界で一番古い縄文土器?
第4講 弥生時代は本当に五〇〇年古くなるのか?
第5講 「邪馬台国」問題は解決されたのか
第6講 なぜあのような大きな古墳を造ったのか
第7講 宮都の繁栄と仏教はどのように地方へ広まったのか
第8講 信長・秀吉の城から長崎の出島まで―考古学の対象の広がり
第9講 最新科学研究と考古学研究のコラボレーション
第10講 現代の発掘基礎知識と考古学の未来
著者等紹介
山岸良二[ヤマギシリョウジ]
1951年(昭和26)東京生まれ。慶應義塾大学大学院修士課程修了。東邦大学付属東邦中高等学校教諭、習志野市文化財審議会会長。専門は日本考古学。千葉大学をはじめ数大学の非常勤講師を歴任。わが国最大の考古学会である日本考古学協会全国理事を通算8期16年歴任、各地の発掘調査事業の指導に従事のほか、一般向け講演やテレビ・ラジオ出演で考古学の啓蒙につとめる。近年は、地元習志野市に縁の「日本騎兵の父 秋山好古大将」関係の講演活動も積極的に展開し、江戸東京博物館などで通算20回以上行う(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
佐藤一臣
akamurasaki