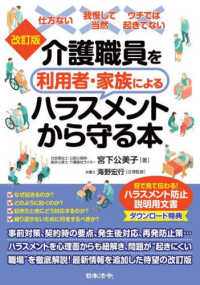出版社内容情報
日本では10人にひとりが経験者といわれる中絶。経口中絶薬の承認から中絶のスティグマ、配偶者同意要件まで、中絶問題の研究家が、世界の動向に照らして日本における中絶の問題点と展望を示す。
昨今、中絶をめぐる議論が続いている。経口中絶薬の承認から配偶者同意要件まで、具体的にこの問題をどうとらえればいいのか。戦後かつて日本は「中絶天国」と呼ばれた。その後、世界が中絶の権利を人権として認めていく流れにあるなか、日本では女性差別的イデオロギーが社会に影を落としている。中絶問題の研究家が、歴史的経緯をひもとき、今後の展望を示す。
内容説明
昨今、中絶をめぐる議論が続いている。経口中絶薬の承認から配偶者同意要件まで、具体的にこの問題をどうとらえればいいのか。かつて戦後日本は「中絶天国」と呼ばれた。その後、世界が中絶の権利を人権として認める流れにあるなか、日本では女性差別的イデオロギーが社会に影を落としている。中絶問題の研究家が、歴史的経緯をひもとき、今後の展望を示す。
目次
第1章 なぜ中絶はタブー視されるのか
補論1 刑法堕胎罪と母体保護法
第2章 日本の中絶医療
補論2 日本の中絶方法の特殊さ
第3章 中絶とはどういう経験か
第4章 安全な中絶
補論3 中期中絶とはなにか
第5章 性と生殖の権利
補論4 経口中絶薬をめぐる情報
第6章 これからの中絶
補論5 不妊治療の保険適用
著者等紹介
塚原久美[ツカハラクミ]
中絶問題研究家、中絶ケアカウンセラー、金沢大学非常勤講師。翻訳・執筆業での活動を経て、2009年、金沢大学大学院社会環境科学研究科博士課程修了(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
駒場
カモメ
ア
jinya tate
乱読家 護る会支持!
-

- 電子書籍
- 宝石少女は涙を流さない 第49話【タテ…