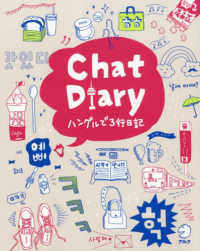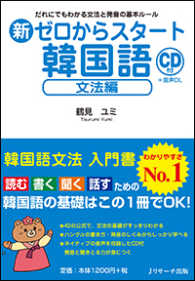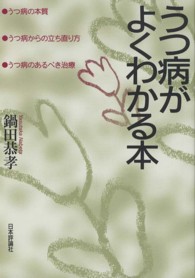出版社内容情報
経済学が前提とする「利己的で合理的な主体」はどこで生まれ、どんな役割を果たしてきたのか。私たちの価値観を規定するこの人間像の謎を思想史的に解き明かす。
内容説明
自分の利益を第一に考えて合理的に行動する主体=「経済人(ホモ・エコノミクス)」―経済学が前提とするこうした人間像はどこで生まれたのか。多くの批判にさらされながらも、それが世界を動かす原動力でありつづけているのはなぜか。「金儲け」が道徳的に蔑まれた古代・中世そして非近代の社会から、近代経済学が確立する「限界革命」の時代をへて、ホモ・エコノミクスが社会の広範な領域に浸透する現代まで。「自己利益の追求」が当たり前の価値として受け容れられるに至ったからくりを、思想史の視座から解き明かす。
目次
第1部 富と徳(金儲けは近代以前にどう受け止められていたか;なぜ人は貧乏人を責めるのか;マンデヴィルとハチスン ほか)
第2部 ホモ・エコノミクスの経済学(ホモ・エコノミクスの語源学;イギリス歴史学派と方法論争;メンガーvsシュモラー ほか)
第3部 ホモ・エコノミクスの席捲(差別・犯罪・人的資本;「緑の革命」―前提としてのホモ・エコノミクス;ゲーム理論と社会的選択理論、そして行動主義革命 ほか)
著者等紹介
重田園江[オモダソノエ]
1968年兵庫県西宮市生まれ。早稲田大学政治経済学部、日本開発銀行を経て、東京大学大学院総合文化研究科博士課程単位取得退学。現在、明治大学政治経済学部教授。専門は、現代思想・政治思想史。フーコーの思想を、「権力」や「統治」を中心に研究する(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。