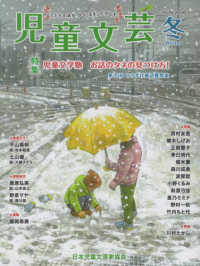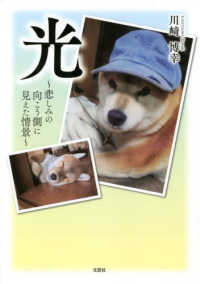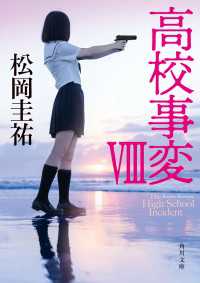出版社内容情報
仕事で目にするグラフや美術館のアート作品など、視覚に訴えかけてくるものは多い。でも、それを読み取り、言葉にすることは難しい。そのための技法を伝授する。
==
ちょっとした子どもの絵、データをもとにしたグラフ、美術館に展示される数々のアート作品。世の中には、言葉以外の形で表現されているものが無数に存在する。しかし、それらから何を読み取り、言葉にすればよいかはあまり教わる機会がない。そこで、様々な実例を挙げながら、特徴の掴み方、解釈の方法、言語化する術、社会との論じ方を段階的に解説する。アートと思考と言語が結びつけば、新たな知の興奮が生まれてくる。
内容説明
ちょっとした子どもの絵、データをもとにしたグラフ、美術館に展示される数々のアート作品。世の中には、言葉以外の形で表現されているものが無数に存在する。しかし、それらから何を読み取り、言葉にすればよいかはあまり教わる機会がない。そこで、様々な実例を挙げながら、特徴の掴み方、解釈の方法、言語化する術、社会での論じ方を段階的に解説する。アートと思考と言語が結びつけば、新たな知の興奮が生まれてくる。
目次
1 基礎編(ヴィジュアル情報の見方と語り方;ヴィジュアル・メディアの特徴は何か?;解釈という段階;グラフ・データの読み取り方;ヴィジュアルの見方―絵を解釈する)
2 応用編(「カワイイ」絵は本当にカワイイだけか?―キース・ヘリング;ポルノとアートの境目―エデュアール・マネの挑発;同じ問題への違う解決―ブランクーシ『レダ』;社会背景を当てはめる―マーク・ロスコと色面構成;比較しつつ対立を乗り越える―藤田嗣治『アッツ島の玉砕』 ほか)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
かんがく
shimashimaon
Танечка (たーにゃ)
はひへほ
hiro