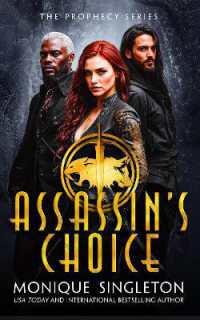出版社内容情報
近年、急速に広まったイヴェント「ハロウィン」。この祭りに封印されたケルト文明の思想を解きあかし、古代ヨーロッパの精霊を現代へよみがえらせる。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
鉄之助
228
ハロウィンは、死者との交流・生命再生の祭りだった。元となったケルトの四季祭り、サウィンから始まる歴史的考察が分かりやすい。子供たちが家々を訪ねて声をかける「トリック・オア・トリート」の本来の意味、が面白かった。もし生きている人たちが、祖先や死者たちのことを忘れ供養(もてなす=トリート)を怠るならば、霊たちは怒り邪悪な事(トリック)を起こすだろう、と警告して歩いているのだそうだ。それにしても、ケルトの文化は、奥深い!2020/10/16
榊原 香織
79
ハロウィーンの元はケルトのサウィン 冬の祭り。 春;インボルク、夏;ベルティネ、秋;ルーサナ。 夏のベルティネの前夜が、ドイツ圏ではワルプルギスの夜(ハロウィーンに近い) シェイクスピアの真夏の夜の夢もこの日の話。2022/10/17
neimu
44
ベルティン祭について知ったのはサトクリフの「太陽の戦士」を読んだ小4の時。妖精の専門的な講義は杉山洋子先生の英文学。大学時代の3週間の欧州の旅、キリスト教を学ぶ旅を重ね、「ヨーロッパの祭り」の異装にときめいた日々、絵画に文学に顕在するケルトの香り、文様、伝承、ブリギッドの名前を最近見たのは再開された「ポーの一族」だった。様々な記憶を手繰り寄せて読んだこの本、父の命は巡り巡ってどこに往き、還って来るのだろうと思う夜。再生、ハロウィンのかぼちゃ、父は戦争中の思い出すかぼちゃを好まなかったのに植えて逝った昨夏。2021/01/21
瀧ながれ
30
ケルトの人たちが祭っていた四季の区切りがはっきりとしていて、日本と似ているようだけど、日本より冬が厳しくて「死」に近いのかと感じた。ライトノベルやゲームで見かける名前がたびたび出てくるのは楽しくて、これからの読書に役立ちそうだ。ケルトの習慣や信仰が、キリスト教とどのように折り合っていったかも興味深く、最後に語られた「ケルズの書」は、全編カラーで見たい(真似して書いてみたい)と思いました。ハロウィンのカボチャの仮装をした子どもの写真が、なんかすごいリアル妖怪ぽくて好きです。2018/06/15
鳩羽
12
近年広まったイベント、ハロウィンの起源はケルトの祭りサウィンにあった。光の季節から闇の季節へと向かう祭りは、死者の霊を迎え入れ、もてなし、過去から生きるための知恵の贈与を受ける祭りでもあった。冬のサウィン、春のインボルク、夏のベルティネ、秋のルーナサ。新旧入れ替わりの周期は規則正しく行われ、それぞれの役割は神格化され、讃えられる。終わることのない円環の営みと螺旋のエネルギーは、装飾にも現れており、異教であるキリスト教に溶け込んでもなお長く残ってきたのは、人生のサイクルと合致することが多かったからだろうか。2018/07/16