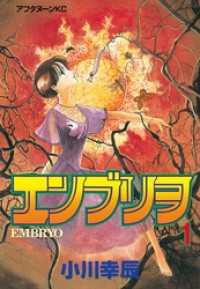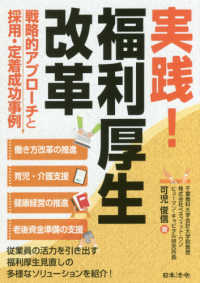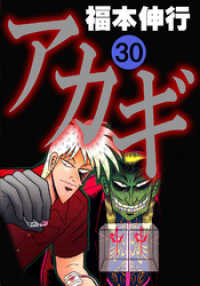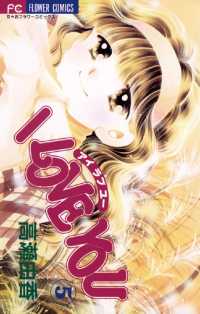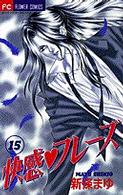出版社内容情報
日本には四季がある。それを彩る植物がある。伝統のなかで培われた日本人の美しい感受性をみつめなおす。カラー写真満載。
湯浅 浩史[ユアサ ヒロシ]
内容説明
日本には四季の美しさがある。それを豊かに彩る植物がある。わが国では古くから植物に関心が寄せられ、暮らしと結びついてきた。日本人と花とのつき合いも深くて長く、すでに万葉人が野から庭に移し愉しむ。ふだん何気なく見ている景観や、ありきたりと思っている行事の習俗など、その主役が植物であることは、少なくない。本書では、豊富なカラー写真を交えながら、環境と伝統のなかで培われた植物に対する日本人の感受性と文化をみつめなおす。
目次
春(ウメ―花、実、技、それぞれに味わい;モモ―ひな祭りと桃の花 ほか)
夏(アヤメ―美しいアヤメ科三姉妹;ウツギ―利用と民俗 ほか)
秋(ハギ―『万葉集』に最も多く詠まれた植物;ススキ―遠のいた役割 ほか)
冬(サザンカ―初冬に彩りを与える花木;ヤツデ―ヨーロッパを驚かせた木 ほか)
著者等紹介
湯浅浩史[ユアサヒロシ]
1940年生まれ。農学博士。東京農業大学大学院農学研究科博士課程修了。一般財団法人進化生物学研究所理事長・所長。東京農業大学農学部元教授。生き物文化誌学会前会長(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
森の三時
22
綺麗だなと思っても、名前がわからないことがあって、草木、花の名前を知っていたら素敵だ。人が名付けたに過ぎませんが、それだけ人との関わりが深く、色を愛されたり、暮らしに用いられてき植物たち。日本人なら知っておきたいとのタイトルが示すように、今はこうした本に教えてもらわないとなかなか見かけないものもありました。2018/01/20
こぽぞう☆
18
図書館の新刊の棚より。月刊誌「武道」に連載されたものを基にしているということで、科学的な話はあまりない。むしろ、歴史かな。日本最古の栽培植物はヒョウタン?万葉集に1番多く詠まれているのはハギ。図版はオールカラー。2017/06/17
双海(ふたみ)
12
ちくまのカラー新書の紙質が好き。身近に花のある生活を送る。2018/03/07
phmchb
6
( ..)φメモメモ『明月記』藤原定家、『尺素往来』一条兼良(p14)/『千載和歌集』、『花譜』貝原益軒(p87)/『物類品隲』平賀源内(p91)/『菅家文草』菅原道真(p134)/『花壇綱目』水野勝元(p135)/『草木奇品家雅見』増田金太(1827)・『南燭品彙』(1884)(p162)/『百椿集』安楽庵策伝(1630)(p187)2020/02/03
Teo
4
ここ最近登山を趣味にしているので野山に見る植物の花が何なのかを知る手がかりと言う気持ちで買った。だが、この本はそう言う分類学的な本ではなくて、春夏秋冬の日本の花々が日本でどんな扱われ方などをしたかと言う本だった。期待した内容とは違ったが、これはこれで楽しめた。ひとつ思ったのは言われてみれば当たり前だが植物によって日本にもたらされた時期が違うと言う点。だから歴史ドラマでその時代に未だ日本に存在しない花が登場してはおかしいのだ。しかしそれを言い出すと酷い植物警察になりそうだw 2017/05/11