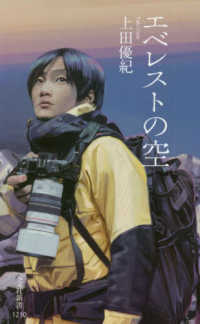出版社内容情報
地震、洪水、噴火……天災を生き抜く知恵は、風習や伝承として受け継がれてきた。各地の災害の記憶から、日本人と天災の関係を探る。
畑中 章宏[ハタナカ アキヒロ]
内容説明
日本は、災害が多い国である。毎年のように、地震、津波、洪水、噴火、土砂崩れ、雪害等が起こっている。古来、日本人はそのような災害と付き合いながら生活を営み、その「復興」と「予防」の知恵を豊富に有していた。そして、それは各地の風習や伝承、記念碑として受け継がれてきたのである。本書では、日本各地の災害の記憶をたずね、掘り起こし、日本人と天災の関係を探っていく。自然に対する感性が鈍ってしまった現在において、必読の一冊!
目次
序章 天災と国民性
第1章 水害―治水をめぐる工夫と信仰
第2章 地震と津波―常襲・避難・予知
第3章 噴火・山体崩壊―山の神の鎮め方
第4章 雪害・風害―空から襲い来るもの
終章 災害と文化―「悔恨」を継承するために
著者等紹介
畑中章宏[ハタナカアキヒロ]
1962年大阪生まれ。作家、民俗学者、編集者(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 2件/全2件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
51
福沢諭吉が表明する民衆観はすこぶる近代的なものであり、民俗に属する人々の信仰や畏怖心から距離を置き、それを前近代的な「人情」と捉えて克服しようとする態度(015頁)。笹本正治(現 県立歴史館長)は、大蛇や竜は水を司り、場合によると洪水などを引き起こすと考えられていたとして、天竜川流域の土石流災害を数多く収集。辰野町の沢底の堂平に、「蛇の池」という小さな底なし沼があり、大蛇が住んでいた。大蛇は大雷雨で山崩れを起こしたとき、一緒に流れて行方がわからなくなった。2017/07/11
どら猫さとっち
10
東日本大震災の日が近づいている今日に読了。古来日本は、地震や津波、洪水に積雪、台風などの自然災害に遭って、そこから多くのことを学び、次の時代の教訓として生かしてきた。本書はそんな自然災害を、我々人間がどのように向かい合い、生きてきたかがわかる。たとえいかなる災害でも知恵を出して、乗りきってきた先人たちの苦悩と生きる力が、文章から伺える。政界の人たちに何としてでも読ませたい。2017/03/04
月猫夕霧/いのうえそう
6
災害に係る全国の言い伝えだなどを広く集めています。結構な数の言い伝えが掲載されていますが、もちろんこれで全部でなく、他にも沢山あるのでしょう。こういった言い伝えを都市化で住民が入れ替わる中で、どうやって伝えていくのか、そんな課題の一助にもこの本がなるのかもしれません。2021/10/11
t80935
5
災害が起こると、その土地の旧地名や言い伝えがクローズアップされることが多い。本来でかれば、地名や言い伝えは日常的な警告として機能するのが望ましいのだろうが、ほとんどが忘れ去られている。多くの地名はシステム上の都合で、当たり障りのない地名に変更されていて不可視となっている。今後の災害多発時代を生き延びるために、改めて日本の土地に染み付いた災害にまつわるあれこれを大事にする時期になってきているのだと思う。2020/12/07
の
5
日本列島を繰り返し襲ってきた天災(水害・震災・噴火・雪害など)が民俗史にどう描かれてきたかを探る本。記紀にも自然の猛威が人と融合して神となる姿が記述されているように、災害大国日本の八百万の神は天災に由来するものが多い。近代以前の民衆は自然に逆らうことができず、信仰による祭儀で精神を安定させる他なかったのだが、経験則から安全な土地の絞り込みや災害時に被害を少なくする対処法といった災害対応はしており、問題意識は持っていたことが窺える。その教訓は、開発工事で環境が変化した土地にも有用なのだろうか。伝えなければ。2018/10/18