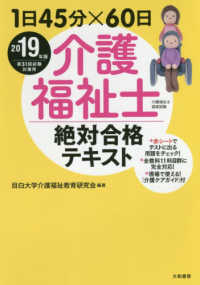出版社内容情報
日本はなぜ「戦後」を終わらせられないのか。その核心にある「対米従属」「ねじれ」の問題の起源を世界戦争に探り、平和憲法の大胆な書き替えによる打開案を示す。
内容説明
日本ばかりが、いまだ「戦後」を終わらせられないのはなぜか。この国をなお呪縛する「対米従属」や「ねじれ」の問題は、どこに起源があり、どうすれば解消できるのか―。世界大戦の意味を喝破し、原子爆弾と無条件降伏の関係を明らかにすることで、敗戦国日本がかかえた矛盾の本質が浮き彫りになる。憲法九条の平和原則をさらに強化することにより、戦後問題を一挙に突破する行程を示す決定的論考。どこまでも広く深く考え抜き、平明に語った本書は、これまでの思想の枠組みを破壊する、ことばの爆弾だ!
目次
はじめに―戦後が剥げかかってきた
第1部 対米従属とねじれ
第2部 世界戦争とは何か
第3部 原子爆弾と戦後の起源
第4部 戦後日本の構造
第5部 ではどうすればよいのか―私の九条強化案
おわりに―新しい戦後へ
著者等紹介
加藤典洋[カトウノリヒロ]
1948年山形県生まれ。文芸評論家。早稲田大学名誉教授。東京大学文学部仏文科卒業。著書に『敗戦後論』(ちくま学芸文庫、伊藤整文学賞受賞)、『言語表現法講義』(岩波書店、新潮学芸賞受賞)、『小説の未来』『テクストから遠く離れて』(朝日新聞社/講談社、両著で桑原武夫学芸賞受賞)など多数(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 2件/全2件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ころこ
36
本書は、他の著作が「だ、である」調なのに対して、「です、ます」調になっています。それは、本書が『アメリカの影』から続く、戦後を考察した一連の著作を通観したものになっていることと通じ、著者の従来の読者を広げて、より一般の読者層に届く努力と読み取れます。ところが、鳥瞰したことにより、そもそも著者の考えてきたことと異なるレイヤーに身を置いていないか、という疑問に突き当たります。『戦後的思考』では、アーレントの古代的な公共性に対して、ルソーの私利私欲から近代的な公共性は立法者の存在により挫折するが、ドストエフスキ2019/10/26
とよぽん
31
戦後74年が過ぎようとしている。戦後の日本について、多少は知っており、分かっているつもりだった。しかし、本書を読んで肝心の根本のところが分かっていなかったのだと気づいた。この本によって、戦後の日本の問題に「入門」できたと思う。政治、国際関係に関しては専門外の加藤典洋氏だが、やむにやまれぬ思いでこの本を書き上げたのだと思う。そして、惜しいことに鬼籍の人となってしまった。まるで遺言のような本だ。2019/08/02
ばんだねいっぺい
29
再読した結果、一回目よりも読みが深まったと言えないことに愕然とする(笑)顕教・密教システムは、ホンネ・タテマエシステムじゃダメか。骨の髄までおじさん的思考の自分を発見する読書となった。2022/10/18
さきん
25
対米従属から自立するというのは、賛成なんだが、9条の二項を変えないで国連や信頼ある世界政府に安全保障してもらうのは、お花畑脳といわざるを得ない。結局フィリピンはアメリカが去ってから南シナ海を中国にかすみ取られた。せめてウクライナやスイス並みに核シェルターを作り、エネルギー自給率を高め、農家や自衛隊obを中心に民間防衛隊やドローン部隊揃えてからアメリカにお引き取り願わないといけない。2025/06/15
テツ
19
現代社会では戦争なんてよっぽどのことがない限り行うメリットがない。反戦活動のためだけだったら過去の悲惨さを学ぶよりも今この時代の戦争から生まれるメリットとデメリットを学んだ方が有効なんじゃないかと思う。ただ先の大戦の前に何があったのか。戦後どういう道を辿り今の日本が創り上げられたのかということを知識として身につけることは鎮魂のために必要だと感じる。大量の生命の上に成り立つこの社会をより良くすることでしか鎮魂のきもちは表せないし、そのためにはまず知らなければならない。今日は終戦記念日だ。2021/08/15
-
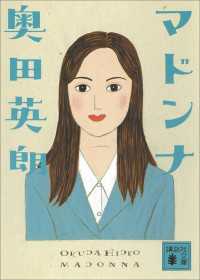
- 電子書籍
- マドンナ 講談社文庫


![[くにたて式]中学勉強法 - 学年順位アップ率96.6%!](../images/goods/ar2/web/imgdata2/48047/4804763511.jpg)