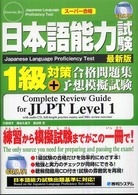出版社内容情報
グローバル化の時代、いま日本が復活するカギは「文化」にある! 外国と日本を比較しつつ、他にはない日本独特の伝統と活力を融合させるための方法を伝授する
内容説明
人口減少、経済停滞を迎える日本。そういったなか、復活のカギをにぎるのは「文化」である。すでにヨーロッパでは、国家規模で文化芸術の推進に取り組んでおり、その成果は様々なところに散見される。また、日本でも地域に根差した文化による地方再生が実践されている。そういった現状を分析しつつ、人間国宝といった形のない伝統や、世界遺産に登録されるような景観を活かすだけではなく、私たちの身近にある小さな文化に注目し、そこから日本人がよりよく生きていくための姿を探る。
目次
第1章 グローバル化の中の文化(グローバル化によって多様な文化の存在が明らかに;世界遺産の誕生とその成果 ほか)
第2章 日本文化とはなにか(恵まれた土地を持つ日本;穏やかな国だから文化財がいまも残る ほか)
第3章 日本の文化政策(日本はどうすれば伝統文化を残せるのか;文化庁ではどのようにして文化財を保護しているか ほか)
第4章 外国の文化政策(外国では文化をどのように支えているのか;文化の先進国フランスの事例 ほか)
第5章 「文化立国」実現のために(暮らしに自然と根付くもの;身をゆだねたい心地のよい日本文化 ほか)
著者等紹介
青柳正規[アオヤギマサノリ]
1944年生まれ。東京大学文学部卒。東大文学部助教授、教授を経て、2005年より、国立西洋美術館長、独立行政法人国立美術館理事長を務める。2013年より文部科学省文化庁長官。東京大学名誉教授、日本学士院会員。国際学士院連合副会長(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
おせきはん
Nobuko Hashimoto
日向夏
yo
-

- 和書
- 歯科医療事故の法的責任