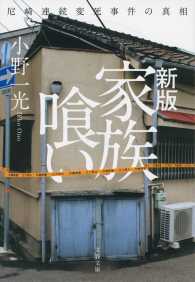出版社内容情報
帰還も移住もできない原発避難民を救うには、江戸時代の「移動する村」の知恵を活かすしかない。バーチャルな自治体の制度化を提唱する、新時代の地方自治再生論。
内容説明
江戸時代、干ばつなど自然災害を被った村は集団で移住することがあった。原発災害による自治体丸ごと避難は、現代に「移動する村」=「バーチャル自治体」を出現させている。ここにこそ自治体の原像がある。原発災害に直面した自治体の動きを徹底検証し、多重市民権の保障という新たな自治体像を提起。さらに「帰りたいけど帰らない」避難民の揺れ動く心情に寄り添いながら、緊急課題となっている住まいの再建方策と、「超長期避難」の制度化を提唱する、ポスト3・11の地方自治論。
目次
プロローグ 自治体とは何か、住民とは何か
第1章 「移動する村」の出現
第2章 原発避難自治体はどのように行動したか
第3章 「空間なき市町村」の歩み
第4章 「仮の町」に込められた意味
第5章 「帰還」でも「移住」でもない第三の道
第6章 多重市民権を保障する自治体へ
エピローグ 国家は僕らを守らない
著者等紹介
今井照[イマイアキラ]
1953年生まれ。専門は自治体政策。福島大学行政政策学類教授。東京大学文学部社会学専修課程卒業。東京都教育委員会、東京都大田区役所勤務を経て現職(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
13
バーチャルな町の意義と隘路(023頁~)。移動する村の場合、移転先には市町村区域に区分されている。一カ所に集中して住むわけではない。人口の少ないところで1500人。被災した役場では、ストレスで怒号が飛び交った(048頁)。福島県内の市長選挙は投票率6割前後(2013年12月)。原発災害の避難とは、避難先を転々とする、これまでよりも遠い地域に仮設住宅や避難先。そして、子育て世代が遠隔地避難(106頁)。仮の町(148頁)。シティズンシップは市民権とか市民性(204頁)。権利と義務の両義性。バランス感覚を。2014/03/07
遅筆堂
10
昨年1年間、南相馬市に住んで生活して、現地の見て、被災者の声を聞いている。ここに書かれていることは現実であって、仮の話でも将来の話でもあい。国はしっかりと考えるべきであるし、原発を動かすのであれば、安全・安心を担保し、自治体の位置づけがしっかりと確保されるべき仕組み作りや法整備がされなければならない。それでないと、未だ避難生活を続けている被災者や自治体の方々の苦労が浮かばれないではないか。2014/10/04
Kentaro
6
原発災害による自治体まるごと避難は現代に移動する村であるバーチャル自治体を出現させている。 これは従来の住民一人に対し、住所は一つであるという仕組みの大前提を崩し、多重の市民権を保障するという新たな自治体像を提起している。 これは、災害で長期に避難を余儀なくされる住民の帰りたいけど変えれない揺れ動く心情にも寄り添いながら実現すべき課題である一方、ふるさと納税制度を発展させ、多重市民権をもつことで、万一の事態に居住先を確保しておくことにも応用できるのではないかと提唱する。2018/08/16
takizawa
5
原発災害によって自治体ごと避難を続けている被災者がいる。対応に追われる自治体職員のルポや被災者へのアンケート調査を通して、そもそも自治体とは何か、住民とは何かを問う本。本書の最も重要な提言は、帰還/移住の二択を迫らず、第三の道(二重の住民登録)の制度化を模索する点にある。思考実験として興味深いなーと思った。あと、緊急時に果たす自治体の役割について考えさせられる。人口規模が一定以上ある自治体だと、本書で高く評価されているような機動的な災害対応は難しいので。2014/03/02
Takako
2
やたらと読み終えるまでに時間がかかってしまったが、学びの多い内容だった。「移動する村」「国家は僕らを守らない」いろいろ納得。2015/07/07
-
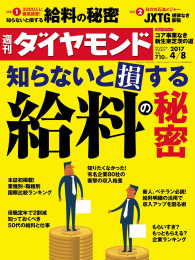
- 電子書籍
- 週刊ダイヤモンド 17年4月8日号 週…
-
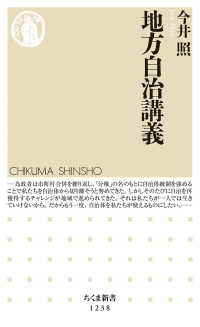
- 和書
- 地方自治講義 ちくま新書