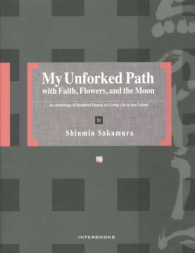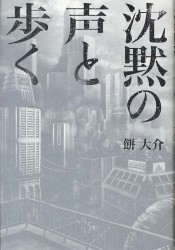内容説明
分析的な視点から、経済データを読むことが求められる時代になりました。でも、学校では、その能力を鍛えてはくれません。だからこそ、自分でデータを読める人は、強力なスキルを身につけていることになり、仕事ではかなり優位に立てます。データを読むための効果的なトレーニング方法は、自分の興味のままに、あれこれグラフや表を読む経験を増やすことです。本書では、読み方によっては奥が深くておもしろい経済データを紹介し、高校生でも、そして大人でも、データ分析の技法を基礎から学べます。
目次
序章 若者の就職状況を示すデータをみてみる
第1章 物価の変化
第2章 産業の動向
第3章 職に就くことのたいへんさ
第4章 日本に住む人たちの将来
第5章 金融の世界での感覚
第6章 国際収支統計の黒字・赤字
第7章 日本経済の成長
著者等紹介
吉本佳生[ヨシモトヨシオ]
1963年生まれ。著述家。関西大学会計専門職大学院特任教授。専門は金融経済論、生活経済学、国際金融論など(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
肉尊
45
トヨタ自動車調査部の方々に資料読解のノウハウを教えるカリスマ講師が、初心者にも分かるよう資料を用いたデータ分析を解説。著者の主張では、安易なグラフ化を避け「まずはじっと表をながめること」(p103)でデータから違和感を感じることが重要だという。傾きが同じなら同変化率を表す「対数目盛」を用いたグラフは活用できるなと感じた。また、変化しないことを読み取ることも大切だという。だが、附属の演習問題は読者に考える機会を与えるだけで、何ら真新しいスキルを与えてくれるものではなかったと感じたことが少し心残りではある。2022/01/01
Tadashi_N
19
適切なデータの正しい見方を覚えることが大切だと思う。GDPは確定値。国債利回りが判断基準。2021/11/21
muu
10
本書はデータの読み取り方を学び、最終的に自発的に元データを探して、グラフを自らが作成できる段階に達することを目標にしている。データを読み取る際にある点に気づくか気づかないとではかなり大きく変わってくる。正確にグラフを読み取る力の必要があり、さらには情報社会化されているご時世には、必須になってくる力ではないだろうか。各章ごとにテーマ分けされており、経済の知識が乏しいせいかわからない内容は多少あったが、就職状況や産業の動向の章は絶賛タイムリーな時期故に、とても興味深い内容だった。再読必須。2016/02/23
シュラフ
7
ビジネスマンの一日は日経新聞を読むことからはじまる。紙面を開けば様々な経済データが出てくる。経済データは世の中の見える化であり、我々は経済データを読み取ることで世の中の状況を把握する。新聞の解説記事を鵜呑みにしてはいけない。意外にも間違った記事が多い。あくまでも自分自身で経済データを読み取って分析することが必要である。分析を行うためには、自分自身で経済データを書き出して・編集して・整理せよ、その過程の中で何かに気づくはずである。それが経済データの正しい分析であると筆者は言う。夏休みあけ実践してみよう。 2013/08/18
hk
3
「人生はマッチ箱に似ている。几帳面に扱うのはバカバカしいが、雑多に扱うのは危険すぎる」 といったのは芥川龍之介だったろうか。 「うるう年」のGDP統計における「マッチ箱」ぶりが勉強になった。1月~3月は通常ならば90日だが、うるう年では「91日」になる。たかが1日だと侮るこなかれ。この1日の有無がGDPに大きな影響を与える。通常年から「うるう年」になるだけで生産力が1%強/(3カ月)上昇し、年率でGDPを4.5%引き上げる効果がある。 これを利用したのが2012年初頭の民主、自民、公明の三党合意による消費2015/11/24