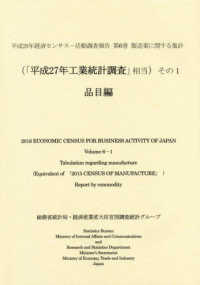出版社内容情報
過ぎ去った日本語は死んではいない。日本人の世界認識の根源には「歌を詠む」という営為がある。王朝文学の言葉を探り、心を重んじる日本語の叡知を甦らせる。
内容説明
「心」「日本語(言の葉)」「和歌」。これら三つは密接につながっている。日本語が発展したのは、和歌のおかげである。日本人の世界認識の根源には「歌をよむ」という営為があるからだ。「心」は日本の伝統文化のエッセンスであり、この叡知を定着させたのは和歌である。しかし、近代以降、西洋文明の獲得と引き換えに、日本語が培った叡知を私たちは失いつつある。その喪失を偲ぶとき、王朝文化における和歌の卓越が明らかになるだろう。本書は、近代文明を相対化する視点をはぐくむものとして、古代文学を捉えなおす試みである。
目次
第1章 『竹取物語』―限りのない美と限りのない心
第2章 タブーと自由―人の心を種としたやまと歌
第3章 「月の影」とその彼方へ
第4章 「あいまいさ」の今昔
第5章 「月やあらぬ」とその英訳
第6章 日本語の限界と無限の表現力
第7章 外縁からのまなざし
第8章 助詞・助動詞のマジック・ミラー
著者等紹介
クリステワ,ツベタナ[クリステワ,ツベタナ][Kristeva,Tzvetana]
1954年ソフィア(ブルガリア)生まれ。1978年、モスクワ大学アジア・アフリカ研究所日本文学科卒業。1980~81年、東京大学文学部国語・国文学科研究生。1984年にソフィア大学博士(文学)、2000年に東京大学博士(学術)を取得。ソフィア大学東洋語教授、中京女子大学教授、東京大学大学院人文社会系研究科客員教授などを経て、国際基督教大学教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
tom
びっぐすとん
in medio tutissimus ibis.
NагΑ Насy
おさ