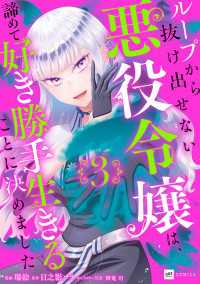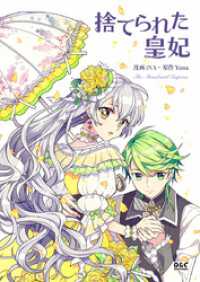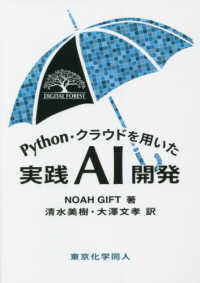出版社内容情報
日本経済の未来にはどんな光景が待ち受けているのか? ?コ川宗家十九代目が、経済の仕組みと現在へ至る歴史を説きながら、身を守るためのヒントを提供する!
内容説明
経済学の初歩から日本経済が現在のように停滞するに至った歴史的理由、そこから導き出される近未来図をクリアに描き、生活防衛へのヒントを提供。徳川宗家十九代目の史眼が冴える、異色の経済ガイド。
目次
第1章 人間と経済
第2章 「分業のジレンマ」と国家の誕生
第3章 お金と国家
第4章 景気、景気対策、バブル
第5章 語られざる生産要素―略奪された富とエネルギー
第6章 関ヶ原からバブルまで―日本経済四〇〇年の歩み
第7章 平成「大停滞」の解明
第8章 これから何が起こるのか
第9章 何をすれば、自分を守れるのか
著者等紹介
徳川家広[トクガワイエヒロ]
1965年東京都生まれ。翻訳家、政治・経済評論家。徳川宗家十九代目にあたる。慶應義塾大学経済学部卒業後、米ミシガン大学大学院で経済学修士号を取得。国連食糧農業機関(FAO)のローマ本部、ベトナム支部に勤務した後、米コロンビア大学大学院で政治学修士号を取得(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
おおにし
10
2010年刊。「新しい日本」のビジョンが私にはピンと来なかったが、これからの行動指針については経済書を読むより、日本人が戦時中をどうしのぎ、戦後の混乱をどう乗り切ってきたか各種の自伝や回想録で学ぶことが大切だという指摘には納得。小説では半村良の「晴れた空」がお薦めとのことで、一度読んでみたい。2015/12/10
あちゃくん
4
前半の、江戸時代から現代にいたるまでの経済学的な解説は、「囚人のジレンマ」があるから市場原理主義はダメなんだと喝破するところとか、分かりやすく小気味いいです。後半の今後の経済予測については、こうなるような気もするしこうならないような気もするし、よくわからないなという印象です。ただ、次のバブルが起こり始めたなと思った時には、終章だけでも読み返そうと思っています。2012/05/11
1.3manen
1
これからの時代、誰も自分を守ってくれない、という前提がある。経済人ではなく、節約する人が求められる(014ページ)。経済学の教科書のような説明があり、囚人のジレンマというゲーム理論も紹介され、基本的な内容にして、生活経済をどう考えるか、提起されている。金融の説明もあるが、評者は、お金を融通することだと思っていた。困った人にお金を回し、お金ができたら返済する。ユヌスのグラミン銀行につながるものがある気もする。エネルギー問題も触れている。上野千鶴子の当事者主権がこの問題にも幅を利かす余地があると思った。2012/07/20
孤独な読書人
1
前半は面白く読めます。後半に行くに連れて著者の考え方に疑問が出てきます。2011/09/29
タイムアウト
0
ギリシャやローマでは略奪が労働よりも上のれっきとした経済行為だった。が、オスマントルコなど周りに強い国ができるにつれて略奪は難しくなっていく。18世紀英国では蒸気の力を活用するようになり産業革命が始まる。化石エネルギーで労働者を代替えできるようになり、アダムスミスのいう「労働が富の源泉」とは限らなくなった。結果あらためてアジアの略奪にのりだせるようになる。身分固定化による完全雇用などで経済の安定化を図っていた江戸時代の日本も、エネルギー革命派で英国の影響下にある明治政府に替わり英のように略奪経済へ…2017/09/29