内容説明
繁華街でも商店街でもない場所にぽつんとある鄙びた酒場。破れた赤提灯、煤けた暖簾、汚れた引き戸。一見客を突き放す閉鎖的な空気を漂わせている。愛想をふりまく看板も品書きもない。どんな店主が経営し、どんな客が集まっているか。どうしてこんな場所に飲み屋があるか。場末の酒場にはそんな疑問がわくが、そこには現代史とも密接な関係を持った歴史があり、個性的な店主と常連客の人情が息づいているのだ。場末の酒場には、酒徒の好奇心を満足させる物語と流儀がある。日常のしがらみに疲れた人間を癒す、酒飲み心の原風景とは。
目次
第1章 場末酒場を探して
第2章 露店換地の飲み屋
第3章 工場街の飲み屋
第4章 色街の飲み屋
第5章 今はなき場末酒場
第6章 場末酒場の流儀
著者等紹介
藤木TDC[フジキTDC]
1962年生まれ。フリーライター。映画やAVの評論から、芸能史、横丁・小路の歴史探索、実話マンガ原作まで、雑誌を中心に幅広く執筆(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
MOKIZAN
11
はまった、間違いなく良書。最終章だけでもいいから読んで欲しい。日常に疲れた時や、中年になればひとり飲みには憧れると思う。最初の一歩の敷居は何処も高く感じるし、一見客と店から値踏みされるのは恐い。数こなすなりでそれを越えれば、綴るところの「清々しい孤独」がきっと迎えてくれます。常連になってわだかまり無い人と話すも良いし、ひとり飲みしたい時はそうさせてもらえるはず。しがらみ優先で自分の飲み方を作れなきゃ、酒飲んでも疲れるばかりなのでは、自分はそうだった。年の半分を締めくくるに相応しい一冊。後半も楽しく飲みたい2015/06/30
justdon'taskmewhatitwas
7
飲み屋で独り飲みした経験が無い。(旅先ならまだしも)場末だろうと一人飲み屋で、女将と語らい、常連客とカラオケを唸るなんて無理無理。終電を一駅手前で降り、遠い夜道を寂寥感と共にトボトボ帰り、冷たい布団にくるまって人生の意義を考える…。この場末飲みの思い出は財産だろうか? (歩いて帰れる程の)度数の低いアルコール(ビールとか)しか飲まない人は幸せだと聞く。・・・わからない。もう少し考える。2022/08/19
go
5
この本を読んで自分は闇市の歴史とかにはあまり興味がないことがわかった。場末の酒場、憧れるがまだ10年は早いかな。2019/09/21
ヒカル
5
行く勇気が無いけど、気にはなっていたので読んでみた。美味いもつ煮込みの背景にある近代日本の歴史なんて考えたこともなかった。ただのうらぶれた街や飲み屋ガイドではなく興味深く読めた。これからも場末酒場に一人で行くことはないと思うけど、見かけたら来歴を勝手に想像しようと思う。2013/03/24
yamanekoken
4
ガイド本ではありません。「場末とは何ぞや」の歴史的考証を軸におきつつ、この中に埋め込む形で「ひとり飲み」の意義を深く、深く考察しています。ところどころに見られる「最近流行りの居酒屋チェーン」みたいな表現が象徴的。最後の方で、自分はそういう飲み方を否定しない、といいつつも行間にちらりと本音が見えます。いずれにしろ、中年以降じゃないとこの味は実感できないんじゃなかろうか?2010/11/28
-
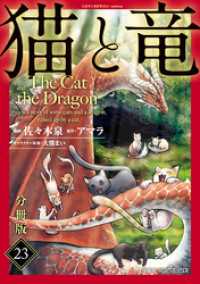
- 電子書籍
- 猫と竜【分冊版】23
-
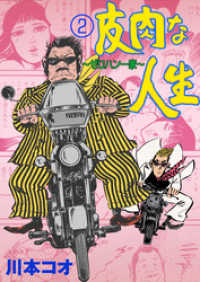
- 電子書籍
- 皮肉な人生 2~ゼロハン一家~ マンガ…
-
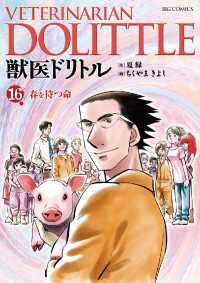
- 電子書籍
- 獣医ドリトル(16) ビッグコミックス
-
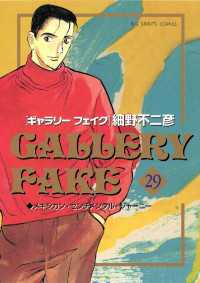
- 電子書籍
- ギャラリーフェイク(29) ビッグコミ…
-

- 電子書籍
- ドクター・ショッピング―なぜ次々と医者…




