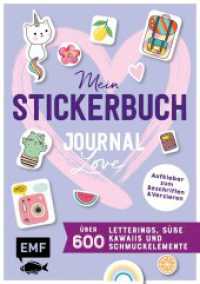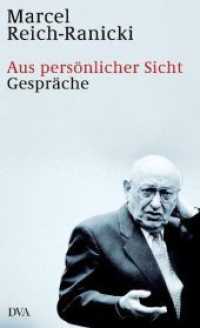出版社内容情報
問題に関係している人全員のメリットを探求する学問、「交渉学」。多種多様な場面で使えるその方法論と社会的意義を平易に解説する。
内容説明
二人以上の人間が、未来のことがらについて、話し合いで取り決めを交わすこと―「交渉」をそう定義するなら、身の回りの問題から国際関係まで、使われる場面はとても多い。本書が扱う「交渉学」とは分野にしばられず、交渉にあたってのフレームワークを築き、当事者全員にメリットが出ることを目指すものだ。小手先のテクニックに終始しない、その基本的考え方と方法、そして社会的意義をわかりやすく解説する。
目次
第1章 交渉とは何か
第2章 交渉のための実践的方法論
第3章 社会的責任のある交渉の進め方―Win/Win関係の落とし穴
第4章 一対一から多者間交渉へ―ステークホルダー論
第5章 社会的な合意形成とは
第6章 交渉による社会的合意形成の課題―マスコミと科学技術
第7章 交渉学についてのQ&A
著者等紹介
松浦正浩[マツウラマサヒロ]
1974年生まれ。東京大学工学部土木学科卒。マサチューセッツ工科大学都市計画学科修士課程修了(1998年)、三菱総合研究所研究員(1998‐2002年)、マサチューセッツ工科大学都市計画学科博士課程修了(2006年)を経て、東京大学公共政策大学院特任准教授。Ph.D.(都市・地域計画)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Yuma Usui
32
学問として交渉を捉え解説した一冊。交渉とは、交渉が破綻した際にとりうる選択肢がバトナで、互いのバトナの間にある合意可能領域をゾーパとしてパレート最適(自分と相手の効用、満足度の最大化)を目指すものとの説明は腑に落ちた。特に面白いのが、交渉には価値生産と価値分割という2つのフェーズが存在し、たとえwin/winでも価値の分配の過多で交渉の成功失敗が決まるため緊張関係が生ずるとの指摘。表面的な主張や立場(position)だけでなく裏にある利害(interest)に着目し準備や交渉を行うことの大切さが学べた。2020/05/29
かず
24
アキアカネさんのご紹介。来週受講する研修の計画主旨に「説得力・交渉力の技術習得」とあり、自分自身苦手意識を持っていたので、予習に読んだ。後半は流し読みになったが、それでも理解した感覚が得られるほど読みやすい。交渉というと、「いかに自分の言い分を通すか」と思われるが、「相手の都合や言い分」も十分に弁えて行うべきであり、かといって自分が損しないために、BATNA、ZOPA、パレート最適といった基本的な考え方を踏まえ実践することが大切だと理解した。根底に信頼感と相手の尊重無くして良い交渉はできないことを学んだ。2020/01/29
かやは
10
交渉は自分の意見が通ることだけが大事なのではなく、意見が通らなかった人も納得できることが大事。しかしこういう経験することで身につけるような事柄は本を読むよりセミナーなりを受けた方が良いな、と思った。2014/11/02
koke
9
話し合うことについて、色々な側面から知りたいと思い手に取った本です。交渉上手はコミュニケーション上手だが、コミュニケーション上手が交渉上手とは限らないといったように、交渉は自己利益を最大化するゲームとしてみればよいようです。一つだけではなく複数の取引材料を扱う統合型交渉が良いというのが印象的でした。相手を隔たったものと捉えつつ、共存共栄を図るというスタンスが前提にあり興味深かったです。2023/12/10
kakaka@灯れ松明の火
5
自分の意見を通したい時に役立つかも・・・と思い手に取ったのですが、しょっぱなから交渉学はそういうものじゃないと言われてしまいました。印象的だったのは、お互いの利益を最大限にするようにしつつ妥協点をみつけ、契約後もよりよい条件を模索し続けること。現実のビジネスでは難しいかもしれませんが、そうする努力はしたいなと思いました。まぁ、そんな場面なかなかないのですが・・・f^^;2010/06/20
-

- 電子書籍
- 「好き」を言語化する技術 プレミアムカ…