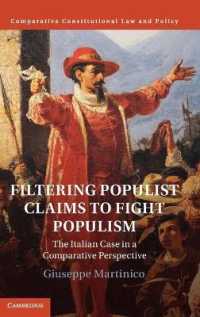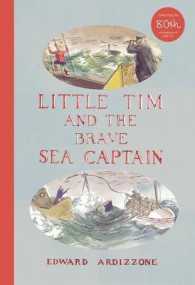出版社内容情報
土器や土偶のデザイン、環状列石などの記念物は、縄文人の豊かな精神世界を語って余りある。著者自身の半世紀近い実証研究にもとづく、縄文考古学の到達点。
内容説明
縄文土器を眺めると、口縁には大仰な突起があり、胴が細く、くびれたりする。なぜ、縄文人は容器としてはきわめて使い勝手の悪いデザインを造り続けたのか?本書では土器、土偶のほか、環状列石や三内丸山の六本柱等の「記念物」から縄文人の世界観をよみとり、そのゆたかな精神世界をあますところなく伝える。丹念な実証研究に基づきつつ、つねに考古学に新しい地平を切り拓いてきた著者による、縄文考古学の集大成。
目次
日本列島最古の遺跡
縄文革命
ヤキモノ世界の中の縄文土器
煮炊き用土器の効果
定住生活
人間宣言
住居と居住空間
居住空間の聖性
炉辺の語りから神話へ
縄文人と動物
交易
交易の縄文流儀
記念物の造営
縄文人の右と左
縄文人、山を仰ぎ、山に登る
著者等紹介
小林達雄[コバヤシタツオ]
1937年新潟県生まれ。國學院大學大学院博士課程修了。文学博士。東京都教育庁文化課、文化庁文化財調査官を経て、78年國學院大學文学部助教授、85年より同教授。2008年3月退官。新潟県立歴史博物館名誉館長(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
翔亀
46
"縄文"という文字を綴った数にかけては日本一ではないかと自負する考古学者の集大成。意外にも手堅く、出土した遺跡に基づき実証的方法により、しかし、民俗学や文化人類学のように縄文人の"心"(著者の用語では「縄文姿勢方針」)を甦らす挑戦をしている。縄文人と一緒に暮らすこはできないので、その試みは推測に過ぎないが、説得力をもたせるぎりぎりのところまで想像力を働かせる。例えば何故縄文土器は器という機能を犠牲にしてまで装飾に凝ったのか。何故翡翠というダイヤモンド並みに硬い鉱物で勾玉を制作したのか。何故1000年とい↓2016/12/12
豆ぽち
21
縄文人は、自然と対峙しながら自然の中に存在し、自然の秩序に従う生物全てに対して、俺たちはもはや動物ではない、人間なんだと自覚するきっかけを獲得したのである。近代以降の自我意識に先立つ、人間意識の萌芽である。人間意識の高揚は、自らが所属する集団の主体性の確立をさらに促した。言葉の言い回しやアクセントなどが他の集団と異なる部分のあることを明瞭に認識する。隣接の他の集団の土器との違いと、自分達の土器が他をもって代え難いものであることを自覚する。自分意識とは、他の集団とはっきり区別されるという認識の上に成立する。2017/12/13
姉勤
21
千年単位で変わらない、ゆっくりとした時間の中の暮らし。約15,000年前から2,900年ごろまで続く縄文時代。豊穣な自然の産物をより利用出来る土器の発明は、今までヒトがしなかった定住を生み、集落と云える「ムラ」、これを囲む里山の様な生活圏「ハラ」を生み出し、故郷や我が家の様な、帰るべき場所を造り出した。その中で縄文人は、様々な道具、社会、習慣やことばなどの日本人のアイデンティティーを生み出し、長大な時間の中で熟成された。以来、色々な人種、文化、概念、宗教、技術が渡来したが、咀嚼し同化する柔軟性を得られた。2015/02/17
佐藤一臣
12
囲炉裏を囲んで、物語を紡ぐ日常を送っていたのではないかという推測は、とてもロマンチックだ。1万年以上続いた縄文人の思想が、フィクションを生み出し、いわゆる日本人の共同幻想の元になっているというのは、かなり刺激的だった。ただ、縄文人が話していた言葉、あるいは書き残していた言葉について、詳しい言及がないのは残念。遺跡には、その痕跡が現在のところ、全く見られないのだろう。著者の一つひとつの推論を、もっと証拠を出して、丁寧に語ってもらいたい。まだまだ縄文には、あっと驚くような秘密が隠されているのだろう。2020/06/16
Nobu A
11
小林達雄著書初読。08年初版、12年第2版。福岡伸一先生推薦本。さすが目が高い。歴史学と考古学の違いを考えたこともなかった。土器や石器等の人工物を始め、住居跡や生活痕跡から当時の人達の想いに馳せる。朝目覚めると食物探しに一日中費やしていた狩猟生活から定住生活に移行し、縄文人の知性が活性化。数メートルの大木の六本柱等、記念物を造営する文化。あれからおよそ2千年。我々の社会は本当に進展したのか。縄文人から学ぶことが多くあるような気がする。タイトルが言い得て妙。縄文時代にタイムスリップしたようで面白かった。2022/10/27
-

- 和書
- あんにょんキムチ