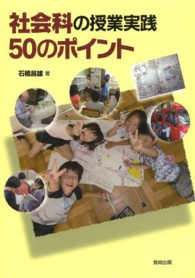出版社内容情報
世界最古の木造建築物として有名な法隆寺は、創建・再建の動機を含め多くの謎に包まれている。その構造から古代人の宗教観を読み解き、日本文化の源流に迫る。
内容説明
法隆寺は世界最古の木造建築として“世界遺産”に指定されている。しかし実は、私たちが目にしている法隆寺は七世紀後半から八世紀初めにかけて「再建」されたものであり、そうしたことがわかったのは一九三九年になってからのことにすぎない。しかも聖徳太子による創建から「再建」達成までの百年間は、仏教の日本化と並行して、古代王朝の内部で激しい権力闘争が起こった時期でもあった。仏教やヒンズー教などのインドの宗教建築を踏査してきた著者が、回廊の構造や伽藍の配置などから古代世界を読み解く、空間的な出来事による「日本」発見。
目次
序章 法隆寺の謎(謎解きのまえに;解き明かされる謎の数々)
第1章 法隆寺をめぐる(門前にて;中門の中で;そして塔と金堂;塔の中で;金堂の中で)
第2章 めぐる作法/めぐる空間(めぐる作法の伝来;五重塔と柱信仰;列柱回廊をめぐる;夢殿へ;祈りのカタチ)
第3章 法隆寺は突然変異か(門の真ん中に立つ柱;なぜ法隆寺だけなのか;法隆寺以前の伽藍配置;法隆寺ファミリーの誕生;謎の柱はビテイコツだった)
終章 日本文化の原点に向かって(タテとヨコ、南北と東西;血統と流儀、そして新創建を進めたのは誰か;空白の誕生、そして大陸起源か日本起源か)
著者等紹介
武澤秀一[タケザワシュウイチ]
1947年生まれ。1971年、東京大学工学部建築学科卒業。同大学院工学系研究科修士課程(建築学専攻)を中退し、東京大学工学部助手(建築学科)。その後、設計事務所を主宰し、東京大学、法政大学などで講師を兼任。現在は東北文化学園大学大学院教授。博士(工学)、一級建築士(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
moonanddai
slider129
の
いりあ
京橋ハナコ
-

- 和書
- 読みがたり大分のむかし話