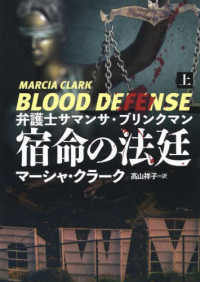内容説明
あらゆる権威は失墜し、そして誰も「絶対の正義」など信じなくなった。「正義」の名の下、憎悪が戦火を拡大する時代だ。だがそれでも、人は「正しさ」なしでは生きてゆけない社会的存在である。では、聖人には程遠い「凡愚」たる私たちは、「正しさ」について何を語りうるのか。本書では、脳死・臓器移植、死刑、愛国心、民主制、環境破壊と南北格差など具体的問題を素材に、価値観が鋭く対立する他者との間に「約束事としての正義」を築きあげる道筋を示す。現代の突きつける倫理問題をみずから考え抜く力を養うための必読書。
目次
第1章 「正しさ」は必要か
第2章 すべての価値を支える価値は何か
第3章 規範は「死」を決められるか
第4章 事実とは何か―事実と社会システム
第5章 科学は正義を決められるか
第6章 他人に迷惑をかけてはいけないか
第7章 選択の自由があるのはいいことか
第8章 暴力をどう管理するか
第9章 国家とは何か
第10章 民主主義は「正しさ」を実現できるか
第11章 「正しさ」の世紀へ
補論 「未来を選ぶ」ということ
著者等紹介
小林和之[コバヤシカズユキ]
1959年生まれ。大阪大学大学院法学研究科修了。博士(法学)。法哲学専攻。保険会社、大阪大学法学部助手などを経て、現在はIT法学教育科研費プロジェクトに従事。自分自身の肉声で思想する希少な法哲学者。卓抜な発想と緻密な論理的構成力をその身上とする
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
テツ
18
様々な社会問題を実例として取り上げながら「正義とは何か」「正しさとは何か」ということを説いている。正義とは感情的な物に左右されずにあくまでも論理的に導き出される物だということが改めて理解出来た気がする。個々人が、勿論僕も含めてだけれど、正義の名の下に自らの正義を振りかざし為す行為について常に精査し疑問を投げかける姿勢が重要なのかな。世間の正しさに、そして自らの信じる正しさに疑問を持ち始めた高校生くらいでも理解出来る内容なので若者たちにもお薦め。2016/11/19
たばかるB
8
10年以上前の評論だけれど哲学的な社会観を具体化した問題として取り上げているため理解しやすく、昨今のマイケル•サンデルとの関連もうかがえる。本書では「おろかもの」は総括して触れてはいないが、個々の問題において、死刑の是非を情動にだけで進める人、十分な知識を持たず他者を差別するナチズム、社会の既存システムに乗じて別社会の人々を考えない狭量な人などといった、共感力や想像力の薄れている人々を指していると読める。問題の「正しさ」は個人の価値観に依存するものの社会を成立させる「理」と他者への配慮を伴うべきだという。2018/12/27
ATS
7
★★☆序でも述べられているように本書は読者を説得する類の本ではなく、とり上げている事柄の様々な側面について考えることで、読者の視野を広げ思いこみ(囚われ)から解放することを目的として書かれている。実際、凶悪犯のなぜ弁護士がつくのか?(人権云々ではなく)、ルールさえ守っていれば利便性のために自動車で人を殺してもいいと是認しているのでは?、国家とはどのような存在か?などを問いかけてきて、固定観念にゆさぶりをかけてくる。物事には様々な側面があることを再認識させ、思索を促してくれる本である。2019/07/05
Mr_meganeboy
3
印象に残った箇所が多くて感想を書くのが非常に難しい。だが、あえて本書のコアとなる一文を挙げるなら以下の文だろう。「『正しさ』を定める規範とその原理は、誰にもわかるように語られなければならない。ここが自然法則との大きく違うところだ。引力の法則を理解していようがいまいが、ビルの窓から飛び出せば下に落ちる。だが、『正しさ』は人に理解されてはじめて『正しさ』としての力をもつ。」僕はこの一文に出会えてだけでも本書を読む価値はあったと思う。世の中には上記のことをを理解せずに【正義】を論じる人が多すぎる。また再読する。2015/05/24
いちはやきみやび
2
死刑、臓器移植、不妊治療、環境問題などの実例を上げながら「正しさ」について理詰めで考えていく本。難解なことばや理屈はなく明快かつ明確な論理で話を進めていく。結論に同意できてもできなくても、理屈で考えるとはこういうことかと分からせてくれる。2024/07/07