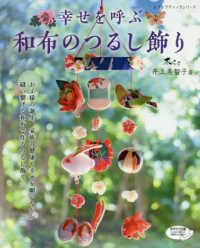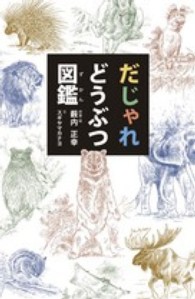内容説明
麻薬、酒、煙草ばかりでなく、賭け事、ゲーム、果ては買物、携帯電話なんてものにまで、ハマってしまう人がいる。それは、なぜか?脳のどこかに、人をモノや行動に溺れさせる秘密が隠されているのだろうか?我々の脳は、進化の過程で生存に有利な様々な働きを獲得してきた。「やめたくてもやめられない」のも、その一つのようだ。それはどんな仕組みによるもので、どのような行動形態をつくってきたのか。本書では、依存を生みだす脳内メカニズムを生物進化の文脈でとらえ、人の肉体と精神の不思議を解き明かす。
目次
第1章 やめたくてもやめられない
第2章 イオンの海のなかで―神経の仕組み
第3章 「欲しくなる」脳
第4章 心のデフレスパイラル―強化学習
第5章 メンタルフレームワーク―記憶と認知
第6章 心の進化が生んだもの
第7章 人間を見る目
著者等紹介
広中直行[ヒロナカナオユキ]
1956年山口県生まれ。東京大学文学部心理学科卒業。同大学院人文科学研究科博士課程単位取得退学。実験動物中央研究所・前臨床医学研究所、理化学研究所・脳科学総合研究センター研究員を経て、現在、専修大学文学部心理学科教授。医学博士
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ノエル
10
依存はこわいです!改めて。ドラッグとかは一度服用すると治らないしもし我に返ったときは後悔すると思うから絶対嫌ですね2015/08/31
smatsu
5
脳神経の構造から、主に薬物への依存症がどのような仕組みで起きるのかを説明する。全体的に学者さんらしい書き口で読みづらい。内容は生物学的な観点からの話がメイン。自分なりにまとめると、依存が起こるのはマイクのハウリングみたいなもので悪い方向のフィードバックループに脳がハマってしまった結果だと。脳の機能上、依存が起きるのはある意味自然なことでやむを得ない。どうすればいいのかみたいな話はあまり書いてないのですが、マイクのボリュームを調整するように脳も依存症にハマらないように調整していくべきと言うことだろうか 2024/07/25
がま
2
ここ最近、危険ドラッグ使用者による事故をニュースでよく目にするようになった。なぜ彼ら・彼女らは薬物に手を染めてしまうのだろうか。そして一度手を出すとなかなか抜け出せないのか。やめたくてもやめられない依存のメカニズムを神経科学や心理学、進化生物学など多角的に追及した一冊。結局のところ、人が薬物依存に陥るのは、脳に何か特殊なメカニズムがあるわけではなく、本来生存に優位となるはずの様々システムが、薬物により好ましくない方向へとはたらいてしまうことによるのである。2014/12/16
ミッツデラックス
1
題名の通り、依存についての話である。内容はほとんど神経科学の話で、依存を引き起こすメカニズムについて脳のどの部位がどういった働きをするのかが書かれている。個人的には、依存はゼロからプラスではなく、マイナスからゼロにもっていくというもの、という考えや快と不快が連なっている、という相反過程理論が印象に残った。全体を通して著者の言い回し(文体?)が最後までしっくりこず読みにくさがあった。2018/04/26
M.I
1
ショウジョウバエでの薬物中毒の実験の様子をぜひ見てみたい 2015/03/07