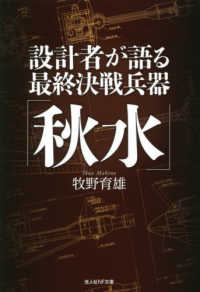内容説明
環境問題はいまや地球全体をおおっている。「地球にやさしく」「自然との共生」…至る所に時代のキーワードが氾濫しているようだ。「自然」や「共生」とは一体何なのだろうか。一八世紀末から始まる欧米の環境思想の系譜を鳥瞰しつつ、その問題点を明らかにするとともに、非西欧社会をも射程に入れた新しい環境学の枠組みを構想する。世界遺産に指定された日本の白神山地のブナ原生林を具体的な事例として、現在の自然保護の考え方を鋭く問いなおす最新の環境問題入門。
目次
序章 環境倫理思想のいま
第1章 環境倫理思想の系譜
第2章 新しい環境倫理をもとめて
第3章 白神山地の保護問題をめぐって
終章 わたしたちはいかにして「つながる」ことができるのか
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
takahiroyama3
4
人生で出会った最高の名著の一つ。これからの自分が、自然と人間の関係を考える際の「原点」となる一冊。人間と自然の関係を「切り身」「生身」という概念装置をもって説明する。即ち、レクリエーション等のために自然利用や、経済目的の森林伐採のような「切り身」の関わりから、地域文化に根差して持続可能に総体として関わり合う「生身」の在り方を、将来像として強調する。既存の環境倫理概念のわかりやすい整理に基づいて、その延長に概念が描かれていることからも、とても勉強になります。とにかく、必読です。2020/12/03
にゃん吉
4
最初の方で、環境倫理思想史を概説し、「生業」と「生活」、「社会的・経済的リンク」と「文化的・宗教的リンク」、「生身」と「切り身」といった概念を用いた著者の視座を提示し、これを前提として、白神山地を具体例とした分析という構成です。環境思想の錯綜した歴史が、よく分かりよかった。著者の視座は、思想としてどういう扱いになるのかは、門外漢にはよく分かりませんが、具体的、多角的に分析し、考えるという、なにか複雑な問題を考え、解決する際に必要な方策に沿うものではないかなと思われました。 2020/05/26
みゆき
4
三章未読。1章の環境倫理の古典はざっと勉強するのにまとまってて分かりやすかった。2章の「生身」と「切り身」という考え方は農業を学ぶ身としては身近に感じられた。2016/12/02
2n2n
4
1章で西洋圏で展開された環境思想を敷衍し、2章では非西洋社会でも通用する環境思想を構想し、3章では具体例として白神山地の自然保護問題を考察するという構成。ポイントは①人間と自然のかかわり方は複雑で多様であり、単純な二項対立で考えるのは誤り。このかかわりは国や地域、あるいは歴史によって様々②環境問題を論じるには、人間と自然の多様な関係性に目を向けるべき。そして、その関係性を繋いでいくことが課題③「自然の知識の伝承」は、将来世代への環境倫理と密接に結びつく。伝承こそ、自然保護や環境保全に関して最も本質的なこと2012/06/10
Hiroki Nishiyama
3
自然から『切れている』自覚を持ち、そこからどう繋がろうとするかが今後の課題。多様な地域の文化や生活を認め、それに応じた解決法を模索せよ。人類vs自然のイメージは古い。現在は自然との『かかわり』が切れてしまっている都市型人間が多い。人間は『かかわり』を持つことにより、持続可能な資源の利用を編み出してきた。今求められるのは、そういった『かかわり』を復活させ、原風景の中に豊かな自然をイメージでき、なんとなくでいいから自然を愛せる人だ。文化的かかわりのない『余所者』が文化的かかわりを復活させる時代に突入している。2011/12/27
-

- 和書
- 踵歩きギプス療法