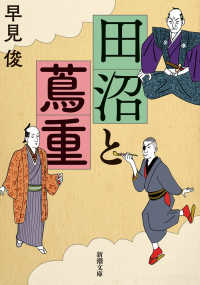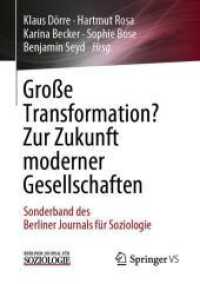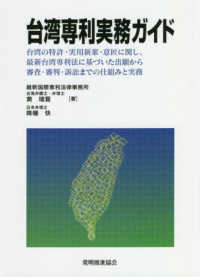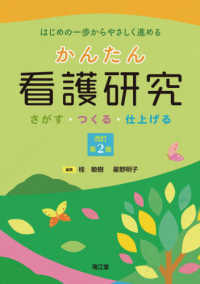内容説明
昭和18年10月、俳優加東大介は大阪中座の楽屋で召集を受け、ニューギニア戦線へ向かった。日本側の敗色すでに濃いジャングル。死の淵をさ迷う兵士たちを鼓舞するために“劇団”づくりを命じられた。“舞台”に降る「雪」に故国を見た兵士たちは、痩せた胸を激しくふるわせた―感動の記録文学である。
目次
四人の演芸グループ
さようなら日本
三味線の功徳
成功した初公演
スター誕生
墓地に建てた劇場
ニセ如月寛多
本格的な稽古
別れの「そうらん節」
マノクワリ歌舞伎座〔ほか〕
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
勝浩1958
11
戦地への慰問団の存在は知っていましたが、戦地で兵士自身が初めは演芸から始まって最後は戯曲や現代劇までが演じられたことは知らなかった。それが況してや加東大介氏であったのですから感慨も一入です。黒澤明監督の『七人の侍』の七郎次がきりっとしたなかに世話女房役としての振る舞いが印象に残っているものですから。それにしても戦後加東氏が地方興行先で遺族の方々からかけられた感謝の言葉は、役者冥利に尽きたものだと思いました。幸せな役者さんであったことでしょう。2015/05/22
勝浩1958
3
10年前に読んでいました。2025/04/26
メイロング
3
こんなに明るい戦記物見たことない! 南方戦線を描いたものというと、どうしても水木しげるの「ラバウル戦記もの」というイメージが強い。なのにこの演芸分隊のさわやかさときたら! 一人一人のキャラが立ちすぎているので、いつアニメ化の話がきても大丈夫ですよ加藤軍曹。前にチラっとTVで映画をやってるのを見かけて、そのまま夢中になってみせられてしまった原作本に、今度も夢中になって読まされてしまった。またやらないかなあ。2012/03/28
ちあき
3
昭和の名優が残した回想録。味方からも敵からも見捨てられたニューギニアの片隅で、「演芸分隊」の座長としてがむしゃらに活動した日々が語られる。衣装も小道具も楽器も舞台装置も(何より食糧も)、とにかくないないづくしの環境でも何事かをなしとげることはできるのだなあ、人間は「娯楽に飢え、娯楽に癒される存在」なのだなあ、と思った。登場人物に注がれるまなざしのやさしさ、戦後の映画やテレビが体現した洗練とは一味ちがう「芸能」のありようも印象に残る。加東さんの再現する篠原曹長の博多弁はちょっと変だけど、どうでもいいや。2009/03/05
rincororin09
1
俳優の加東大介による異色の戦記。日本軍敗色の濃いニューギニアのジャングルの中で慰問のために作られた兵士たちによる劇団のおはなし。中学生か高校生の時にテレビで映画を観て涙腺が崩壊した記憶がある。そしてやっぱり今読んでも雪の場面では涙腺が崩壊。2014/02/07