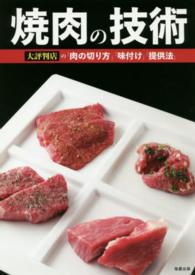内容説明
アメリカ南部の黒人が話す英語はなぜ東北弁になるのか?『ライ麦畑でつかまえて』と『危険な年齢』の関係は?「がってん承知の助」の原文は?翻訳家。なんて因果で罪つくりで、面白い商売。英語と日本語の狭間で身もだえしつつ、コトバから文化を照射する。翻訳あれやこれやエッセイ。
目次
翻訳うらばなし
いまは早くも死語なれど
ピーターとペーターの狭間で
1 ~ 1件/全1件
- 評価
pure-oneの本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
harass
35
以前から気になっていた本でようやく手に入れた。翻訳家のエッセイ集。読みたかった翻訳にまつわる裏話などには違いないが、いい意味で軽い記事がほとんどだった。勝手に思い込んでいたせいでもあるが、個人的に唸らせられた話はほんのちょっとだった。まあ一般向け雑誌用のエッセイであるし、翻訳ヲタ向けではないのからか。むむと思うところもあった。原作者は自分の書いた文章の意味をすべて心得ているわけではないという、著者の確信は正しいと思う。2015/10/11
清少納言
8
言葉は難しい。だから翻訳は大変だ。本来の言葉の意味、日本での意味、時代背景ごとの意味、一つの言葉にはいく通りもの意味があり、それに追い付いていかなければ成り立たないというのは、想像を絶する。作者は、ポジティブで、文章も面白いので、すらすらと読める。30年前の本だが、作者が時代の先端をいっていたことが、よくわかる。「老人と海」が、「じいさんと海」では、なんか困ります(笑)2014/07/02
三柴ゆよし
7
グルジアをジョージアと呼ぶなんて!という話。2015/04/29
あかつや
5
翻訳家の青山南によるエッセイ。題は「各国固有の名詞は各国の発音通りに発音し、表記」するという「原音主義」から。イギリス人ならピーター、ドイツ人ならペーターというわけだ。こういう翻訳の細かい部分を面白おかしく紹介している。アメリカ南部の黒人訛りが翻訳で謎の東北弁になるのとかほんと不思議だよ。あとはこれが書かれた80年代後半時点の変な使われ方してる外来語の紹介が面白かった。さすがに古く、現代における使われ方ともまたズレてきていて、この言葉の変化そのものがすごく楽しい。それと使ってみたい汚い言葉、共感するわあ。2019/09/10
しまうま
4
「1人の物書きが翻訳に関する話を書いてみました」程で、たくさんの与太話が出てくるが、それらがいちいちクセがあって面白い。岸本佐知子さんの『気になる部分』とはまた違い、まさに翻訳家ならではの文章がずらり。僕からすれば大江健三郎が「悪文」だという認識は新鮮だったし(それはひとえに僕の未熟さが理由だとしても、だ)、生前のブローティガンの様子が見てとれたのも歓びのひとつだ。翻訳を「作業」というよりも「発掘」的感覚で行っている著者に好感がもてる。2012/09/18
-
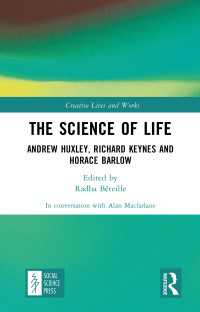
- 洋書電子書籍
- The Science of Life…