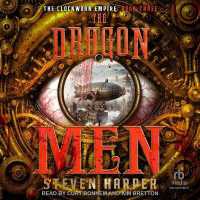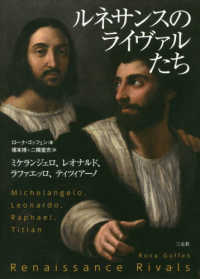出版社内容情報
かつて都大路に出没した鬼たち、彼らはほろんでしまったのだろうか。日本の歴史の暗部に生滅した〈鬼〉の情念を独自の視点で捉える。
【解説: 谷川健一 】
内容説明
かつて都大路を百鬼夜行し、一つ目、天狗、こぶ取りの鬼族が世間狭しと跳梁し、また鬼とならざるを得なかった女たちがいた。鬼は滅んだのだろうか。いまも、この複雑怪奇な社会機構と人間関係の中から、鬼哭の声が聞こえはしないか。日本の歴史の暗部に生滅した〈オニ〉の情念とエネルギーを、芸能、文学、歴史を捗猟しつつ、独自の視点からとらえなおし、あらためてその哲学を問う名篇。
目次
序章 鬼とは何か
1章 鬼の誕生
2章 鬼を見た人びとの証言
3章 王朝の暗黒部に生きた鬼
4章 天狗への憧れと期待
5章 極限を生きた中世の鬼
終章 鬼は滅びたか―あとがきにかえて
1 ~ 2件/全2件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
藤月はな(灯れ松明の火)
68
ずっと気になっていた本。意外と『日本霊異記』や『今昔物語』など説話を例にして柳田国男の一つ目神論や伊勢物語の鬼は藤原権力を象徴していたなど展開しているのが興味深かったです。特に能における鬼(般若としての橋姫、般若になる前段階である半生としての清姫)から伺える女性の情念と悲哀から、当時の仏教で女性は決して往生できないとされた理由が垣間見えるのが目から鱗が落ちました。紹介しているので分かりやすかったです。高田崇史作品にも出てきた鬼=朝廷にまつろわぬ者に加え、民衆の代弁者でもあった論も面白かったです。2014/07/23
Koichiro Minematsu
64
鬼滅の刃ブームにのっかかり、手にした本。約50年前に書かれたものだが、作者の執念とも言える、まさに研究本。歴史、古典、昔話などあらゆる視点から鬼の様態を追求した研究。百鬼夜行、土蜘蛛、天狗、般若など。個人的には第2章の「鬼を見た人びとの証言」が面白い。研究の結果、最終章で「鬼は◯◯」と言い切る。まさしく鬼滅の刃につながった。2021/02/28
榊原 香織
27
鬼、天狗、山姥、能の鬼女、等。日本の古典からの研究。 1971年刊行なので、今読むと際どいところもあるけれど。 山姥に対する憧れがほんのり感じられます。2020/09/28
yamahiko
25
古典文学や先達の研究に敬意をはらいながら、丁寧に論を進めていく。こちらの気持ちに切々と響く名文。久しぶりに手放しで素晴らしいと思える本に出会えました。2017/09/18
春風
24
鬼とは、凄きモノを、兇悪なるモノをいい、人間の否定形と見られることが多い。しかし本書では、殊に中世説話の中の鬼を取り上げ、非常なる人間性の発露、その極致に於いて、有情が非情へと転化するという、人間性に過ぎる故に鬼と成るという逆説の上に鬼論を進める。著者のいう鬼とは、どこまでも人間なのである。そういう意味に於いて鬼は恐怖や畏怖で括るには違い、寧ろ憧憬の念を抱かれる存在という面が確実にある。それは、或いは規矩に馴染まぬであるからか。また、評論家の著者の〈能〉の般若考は、以上の論説の具体化として見える。2020/05/06