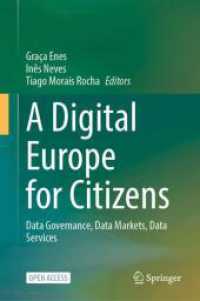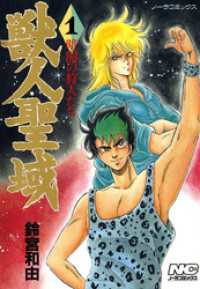出版社内容情報
沖縄に米軍基地が集中し、その状態が続くのはなぜか? この問題の解決策とは? 基地問題の「解決」をめぐり論争が続く今、基地研究の成果を世に問う渾身の書!
内容説明
沖縄への米軍基地の集中が続く。日本における同基地の面積の七割強がこの地にある。米兵による事件、米軍機などによる騒音被害は沖縄の社会・経済に深刻な影響を与え、選挙を通じて示される沖縄の民意は、基地の集中を拒絶している。にもかかわらず、長きにわたり解決策を見出せずにいる。そもそもなぜ、沖縄に基地が集中し、それが続くのか。その経緯を明らかにし、地理的な必然とも、安全保障をめぐる戦略上の必然とも言い切れないことを示す。その上で、基地問題の「解決」へと一歩を踏み出すための選択肢を提示した決定的な書!
目次
第1章 基地をめぐる揺らぎ
第2章 「日本防衛」―日米それぞれの思惑
第3章 視界から遠ざかる基地
第4章 成長する基地
第5章 基地問題の解決につながる政策とは?
終章 日本の基地問題、その展望
著者等紹介
川名晋史[カワナシンジ]
1979年生まれ。青山学院大学大学院国際政治経済学研究科国際政治学専攻博士後期課程修了。博士(国際政治学)。現在、東京工業大学リベラルアーツ研究教育院准教授。専門は米国の海外基地政策(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
skunk_c
68
アメリカの海外基地政策の研究者の書。1968年~72年のベトナム戦争期と沖縄施政権返還の頃の、日本の米軍基地再編のプロセスを詳述。この頃アメリカははっきりと「日本の米軍は日本防衛の為に駐留しているのではない」と宣言していた。当時は冷戦下で「核の傘」で日本を守るが、日本に対する直接攻撃は自衛隊が対処せよとの発想。その後ニクソンドクトリンにより東京周辺の基地が整理・統合されたが、同時沖縄の海兵隊が固定されていく。1968年段階では沖縄の海兵隊は本国へ撤収予定だった。著者はこの変化を「絶妙のタイミング」とする。2022/12/23
ちぃ
21
沖縄旅行で、軍用地を扱う不動産屋が目につき、また改めて基地が身近にあることを実感して本書を手に取った。東京にも横田基地があって、まぁ近くまで行けばさすがに存在感あるけれど、普通に暮らしていてそれを実感することは多くない。それが筆者のいう「隠されている」ことであり、あとは規模によるものなんだろう。20年前だったら素直に不要と言えたかもしれないけれど、最近はそうは言いにくい。地政学的に沖縄が重要なのはそうなのだが、結局のところ投資したものを維持すること、移転にもコストがかかることでそのままになっている側面も。2023/05/23
二人娘の父
13
基地という存在を、その成立から存在意義、存在しつづけるいくつかの要素に至るまでを探究する労作。タイトルおよびテーマとして沖縄が掲げられるが、決して沖縄の基地問題だけを射程においた研究ではない。基地があることによって、その地域や住民、そして行政・国家がどんな思考をたどり、具体的な施策を選ぶのかを考えさせられる。結論は、沖縄でなくてもいいが、さまざまな歴史的経過から沖縄にあり続けることが容認・黙認されている。沖縄基地問題を複眼的・多角的に考察するためには必読の研究である。2022/12/17
大泉宗一郎
6
なぜ沖縄に基地が集中するのかを日米の一次資料を辿りながら詳らかにする研究書。ベトナム戦争時、沖縄基地は経費削減を理由に撤収する予定だったが、日本の”国民感情”に配慮し首都圏の基地を縮小したことや(関東計画)、米軍を引き留める日本政府の要望等により、本土から沖縄に基地機能を移転し、沖縄の基地負担率が相対的に拡大。著者は、基地が集中した理由として地理的理由よりも上記のような政治的思惑が大きいことを挙げ、今日の問題は沖縄が「本土の『身代わり』」となった結果だと指摘。そこに至るまでの過程がつぶさに詳述され、圧巻。2024/02/04
Hiroki Nishizumi
4
分かりやすい文章で参考になった。ある意味なし崩し的に進んだこと、パレート最適のごとく問題の大きさが大きな要因であること、現状維持バイアスが大きいこと、などなど正しく無いけど変わらないことのようだ。私たち一人一人が動かなければならないと思う。2023/02/05