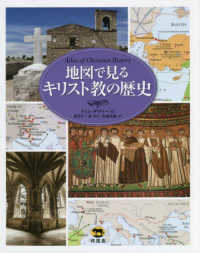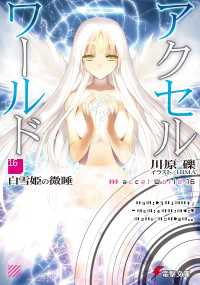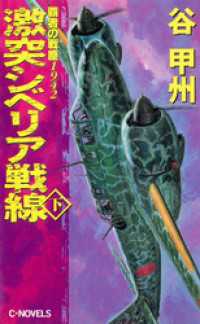出版社内容情報
国民的知識人、柳田国男。その思想の底流にはクロポトキンのアナーキズムが流れ込んでいた! 尊皇の官僚にして民俗学の創始者・柳田国男の思想を徹底検証する!
(すが) 秀実 「すが」は「いとへん」に「圭」[スガ ヒデミ]
木藤 亮太[キトウ リョウタ]
内容説明
「日本」民俗学を創始した柳田国男。その仕事は農政学、文学など多岐にわたる。夏目漱石と並び「国民的」知識人ともいうべき柳田は、吉本隆明、柄谷行人ら戦後の知識人からも熱心に論じられてきた。だが、若い時期に、アナキストたるクロポトキンから決定的な影響を受けたことは全く知られていない。これこそが、柳田の文学、農政学、民俗学をつなぐミッシングリンクであり、尊皇の国家官僚たる柳田の相貌も、そこから立ち現れてくる―。本書は、まったく新しい柳田像を提示した、画期的な書である。
目次
1 柳田国男をめぐる象徴闘争(民俗学・農政学・文学;保守主義者という立場;「日本」は存在しない)
2 帝国主義国家官僚のクロポトキン(文学と革命;民俗学と共産主義;農政学と天皇制)
3 法・民主主義・固有信仰(『山の人生』をめぐって;民主主義の条件;天皇制とアジア主義;祖先崇拝と祖先以前性―エピローグにかえて)
著者等紹介
〓秀実[スガヒデミ]
文芸評論家。1949年生まれ
木藤亮太[キトウリョウタ]
近代日本文学研究者。1990年生まれ。近畿大学文芸学部卒(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件