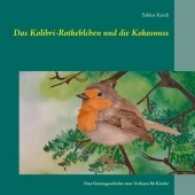出版社内容情報
日常における〈自明なもの〉を精査し、我々の経験の構造を浮き彫りにする営為――現象学。その尽きせぬ魅力と射程を粘り強い思考とともに伝える新しい入門書。
内容説明
日常においてはいつも素通りされている豊かな経験の世界がある―。“自明”であるがゆえに眼を向けられることのないこの経験の世界を現象学は精査し、われわれにとっての「現実」が成立する構造を明るみに出す。創始者フッサール以来続く哲学的営為の核心にあるものは何か。そしていまだ汲みつくせないその可能性とは。本書は粘り強い思索の手触りとともに、読者を生と世界を見つけなおす新たな思考へと誘う。
目次
序章 「確かさ」から「自明なもの」へ
第1章 「確かである」とはどういうことか?―「あたりまえ」への問い
第2章 「物」―流れのなかで構造をつかむということ
第3章 本質―現象の横断的結びつき
第4章 類型―われわれを巻き込む「形」の力
第5章 自我―諸現象のゼロ変換
第6章 変様―自我は生きた現在に追いつけない
第7章 間主観性―振動する「間」の媒介
終章 回顧と梗概
著者等紹介
田口茂[タグチシゲル]
1967年生。北海道大学大学院文学研究科・文学部准教授。早稲田大学大学院文学研究科修士課程修了、同研究科博士後期課程にて単位取得後、1998年よりDAAD奨学生としてドイツ・ヴッパータール大学に留学、2005年同大学にて哲学博士号取得(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
本屋のカガヤの本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ころこ
26
他レビューに「読み易い」とあったのを偶然見つけ、今回読んでみました。数日前に読んだ『つながりの作法』の綾屋、熊谷両氏の話にある、「つながらない身体」と「つながりすぎる身体」の話は、健常者にとって現象学的だといえるでしょう。機能していない自明性を捨て、自己をリアルな世界へと開くホラー映画は、まさに現象学そのままといえるでしょう。映画や美術や医療など現象学の展開は、かえって分かり易い。ところが、フッサールの現象学といえば、昔の哲学の悪いイメージのまま漢字の熟語が頻出し、前期と後期で少しずつ違うといった、言葉遊2018/06/25
cape
26
あるものがあるということ、私が私であるということ、本当にそうか。「確かさ」の裏を取ろうとすると、疑義が生じる。フッサールの現象学を解説するのではなく、それを実際にやってみせる。「物」「本質」「類型」「自我」「変様」など、どれも「確か」でない諸現象をわかりやすい事例で考えさせてくれる。こうした思考が何かを生み出す気がする。あるいは「確か」と思えるものが貴重に思えてくる。人の強さ、たくましさ、しなやかさにつながる思考だと思った。もちろん、そんな考えも「確か」ではない。2016/09/04
ほし
15
フッサールによって提唱された現象学は、いったい物事をどのように捉え、考えるのか?この本では、そんな現象学の考え方が解説されています。やや議論が入り組んでおり難しいところもあったのですが、あらゆる物事を「孤立的に実態として確保」されているものとして見るのではなく、「流れ続ける現象のなかに、その運動の参照点として現れるもの」として捉えるのが現象学の大きな特徴なのだと理解しました。特に他者との関わりを論じた、間主観性の議論には大いに刺激を受けたとともに、SNS時代のコミュニケーションの異質さを改めて感じました。2020/11/28
ポルターガイスト
7
今まで読んだ現象学入門的な本の中ではいちばんよかった。前書き読んで絶対波長合うと思って気になってたが,当たり。平易な言葉遣いで現象学の手触りをしっかり伝えてくれる。現象学そのものの入門というよりその思考の跡をなぞるような本を目指したという筆者の目論見は達成されていると思う。ただ個人的には「私」や間主観性(他人)についての章は納得ができなかった。なぜかはわからない。自分の頭では説明できないけど。たぶん「他人」の捉え方という点においておれが大きな課題を抱えているからだろう。本書の説明でそれは癒やされなかった。2022/09/06
しゅー
5
★★★★現象学とは『確かさ』を支えている『自明なもの』の次元を探る営みである。それまでの哲学が思考の対象としてきた『物』、『本質』、『自我』、『他者』は『実体』ではなく、現象の流れをさまざまな仕方で屈折させる媒介点でしかない。『世界』や『人間』が生起してくる『場』まで遡ろうとする、その思考はスリリングだ。本書は、現象学の用語に拘らず、フッサールその人の思考も踏み越えながら、著者の考える現象学を提示する。通常の入門書を読んだ後で本書に接すると、現象学の厳めしい用語の本来の意味合いを感得できて、助かると思う。2022/02/06
-
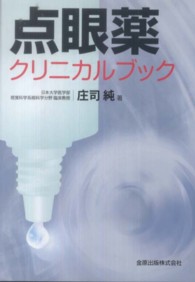
- 和書
- 点眼薬クリニカルブック