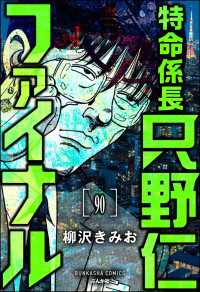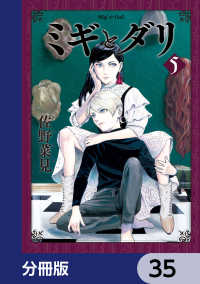内容説明
皮膚は自己と環境との境界である。家は公と私を隔て、国境は国を隔てる。これら境界は本当は一体何を隔て、われわれに何を強いているのか。境界を越えるという経験はいかなる意味をもちうるのか。境界を越えて、われわれはいかに他者と出会い、世界とつながることができるのか―。幾層もの境界を徹底的に問い直し、内/外を無効化する流動的でダイナミックな存在のあり方を提示する。身体・自己・世界の関係を考察してきた著者が、流体の存在論なる新境地に挑む。
目次
始原の海のディオゲネス
第1部 変身(ファッションと産まれることの現象学;見つめられることの現象学;痛むこと、癒されること;食べられること、食べること)
第2部 海と空気(流体のオントロジー;都市とウィルダネス、天井も壁もない家;家のないこと;コスモポリタニズム;海洋惑星とレジリエンス)
著者等紹介
河野哲也[コウノテツヤ]
1963年生まれ。慶應義塾大学大学院文学研究科博士課程修了。玉川大学文学部准教授などを経て、立教大学文学部教育学科教授。専門は、哲学・倫理学。哲学を用いて、環境・倫理・身体に関して思考を拡げる(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
袖崎いたる
6
意味や無意味や非意味について悶々としているところに本書の記述は啓示だった。鷲田清一の仕事の紹介によってその意義についての示唆を受けられたし、LGBT問題の方にも寄せて考えられる。ジンメルの両価的なものという概念はまさに彼等にとっての性を〈ふつう〉指向においての同調と捉えられるし、そこから浮いてしまう拘泥は個性化に当たるといえる。つまりファッション。その脱根拠性はあらゆる権力を免れようという身振りを促す。そして意味のないものの価値という方に導く。そこはコスモポリタニズム。理想を凡庸な悪と読み換える試みも。2017/08/03
たか
5
今回のセンター現代文で採用された書籍です。2020/06/30
ハチアカデミー
4
境界は、自/他の区別を作りだし、どこに境界を引くのかによって「自」の範囲は変化し、世界の内部と外部も分けて認識される。本書では、その境界がどのように認識されるのかを、身体から服、所有物(車・家など)、集団(地域・国家)へと範囲を広げながら論じられていく。第5章で紹介されたティム・インゴルドの「ウェザー・ワールド」という世界観には目を開かされた。世界は流動的なものであり、予測に限界のある複雑さを持つ。ならばこそ、その世界に合わせ、運動する・変化する自己を獲得することの大切さを説く。生きるための哲学書である。2014/08/02
黒木美波
2
2020年のセンター試験・国語で題材となったものです2020/02/22
坂口衣美(エミ)
2
合わなかった。うーん、と思うところが多くて読みづらい…。ドーキンスの表現型ってそういう意味なんかなーとか(p144)。あと習慣化されたことをするよりエキサイティングなことをするほうがいいのか?と。どっちがいいかは個人的な性質の問題だと思ってしまった。全体的にまとまりがなく、ロマンチック印象。2014/08/14