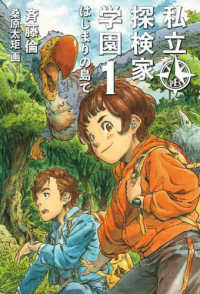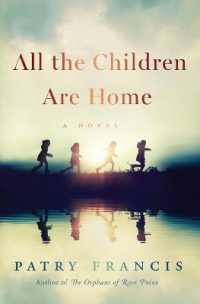出版社内容情報
仏教の教理を絵で伝える説話画をイコノロジーの手法で読み解くと、中世日本人の死生観が浮かび上がる。生活史・民俗史をも視野に入れた日本美術史の画期的論考。
内容説明
人は、この世に生まれ、年老い、病を得て、死ぬ。仏教に謂う「四苦」を日本人はどのように捉えてきたのか。教理経論を絵で伝える「仏教説話画」を、イコノロジーの手法で読み解くと、苦しみに対峙する中世日本人の心性が浮き彫りになり、時空を超えて、その知=死生観・宇宙観が現代によみがえる。生活史・民俗史をも視野に入れた、日本美術史の画期的論考。
目次
第1章 生まれることは苦しいか?(四苦とはなにか;「生苦」とはなにか ほか)
第2章 老いの醜さ・老いの尊さ(老いはいつから始まるか;老いの醜さ ほか)
第3章 病の三態と「病草紙」(病のイメージ;路上の病人 ほか)
第4章 死を超えて(死ぬのはいつも他人;「死苦」のイメージの二面性―哀惜と嫌悪の精神史 ほか)
著者等紹介
加須屋誠[カスヤマコト]
1960年東京都生まれ。京都大学文学部哲学科美学美術史専攻卒業。同大学院文学研究科博士後期課程単位取得退学。博士(文学)。帝塚山学院大学助教授などを経て、奈良女子大学文学部教授。専攻は日本仏教美術史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
こきよ
64
仏教で言うところの〝四苦〟、生老病死を仏教説話画から読み解くという試みの本書。寺社等に現存する画をいわゆるイコノロジー(図像解釈学)の方法論を用いて綿密に分析研究してある。現代は(特に先進国に於いて)〝死〟から遠い時代とも言える。しかし近現代に至るまでの如何なる時代、地域に於いても〝死〟はより身近なものとして存在していたのがよく解る。抗い難い故の生死観とも言えようか。2015/05/05
姉勤
23
戦乱、疫病、自然災害、そして運命。科学や医療、情報操作やインフラによって、不快なるものが目の届か無い現代。生まれること、老いること、病むこと、死ぬこと。今日に比べ皮膚感で感じざるを得無い中世。人々の恐怖や不安をほどくため、寺院や巷間で掛け軸や絵巻などの図像を以って、説き、話す目的で描かれた仏教絵画とは裏腹に、無常を説いた九相図が屍体愛好や覗き趣味の背徳を宗教画であることを隠れ蓑としている解説は肯んせざるを得無い。宗教(日本仏教)は、死にゆくものと、そして看取るもののためのもの。現実はひと一人では荷が重い。2016/02/14
koz
2
仏伝の重要なエピソード、悉達太子の四門出遊の四苦《生老病死》を伝える説話画の解釈を試みる本書。新鮮なのは、出産がみな座産姿で描かれている生苦図、 病魔の道具は小槌が決まりという病苦図。また死した女人が朽ちていく姿という強烈なモチーフで有名な九相図では、詞書の往生要集ではなく隋の摩訶止観に於ける記述に沿っているという点も面白い。京都・山越阿弥陀図の掌から伸びる五色の糸は、終末看護における死にゆく者の手に繋がれる「実用品」でもあった。臨終行儀の心遣いと、長明・発心集の巻七第五の彗眼。人は変わらぬものかは2015/11/27
むっくり
2
絵に表された図像からその絵の目的、受容、当時の社会状況を読みとく。九相図を鑑賞する際、エロスから信仰心へ移行していく心という指摘が的確だと思った。仏教のみならず、日本古代・中世の文学や歴史に興味がある方におすすめ。2012/04/07
らいるー
1
生老病死。誰もが一度は耳にしたことがあるのではないか。仏教画をもとにその時代を読み解いていく。いや、その時代をもとに仏教画を読み解くのか。深いね。2023/03/30