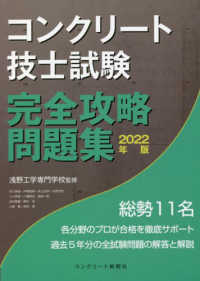出版社内容情報
モース『贈与論』などの民族誌的研究の成果を踏まえ、贈与・交換・互酬性のキーワードと概念を手がかりに、日本文化における贈答の世界のメカニズムを読み解く。
内容説明
贈答とは単なるモノのやりとりではない。恩への返礼にせよ、義理への対価にせよ、はたまた親愛の証しにせよ、特定の機会での贈りものに媒介された儀礼的行為である。中元や歳暮のやりとりをはじめ、被災地への義捐金やボランティア活動が意味するものはなにか。人類学者モースの『贈与論』など民族誌的研究の成果を踏まえ、贈与・交換・互酬性のキーワードを手がかりに、日本文化における贈答の世界のメカニズムを読み解く。
目次
序章 贈答の世界を解読するために
第1章 贈答の過去と現在
第2章 贈答の仕組み
第3章 贈答の諸相
第4章 贈答と宗教的世界
終章 贈答と現代社会
著者等紹介
伊藤幹治[イトウミキハル]
1930年東京都に生まれる。1953年國學院大學大学院文学研究科修士課程修了。国立民族学博物館教授、成城大学教授、成城大学民俗学研究所所長を歴任。国立民族学博物館名誉教授、文学博士。柳田国男全集編集委員。第一回澁澤賞・第一八回南方熊楠賞受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
takao
2
ふむ2024/03/20
1.3manen
1
贈答とは儀礼的行為である(表紙カヴァー裏及び013ページ)。贈与とは贈り物そのものも意味する(021ページ)。譲る行為は二宮尊徳の推譲を想起するが、互酬性とは交換の背後に潜み、交換のあり方を総体として規定する概念である(025ページ)。K.E.ボールディングの互恵性概念ももう少し検討してみたいと思った(081ページ)。レヴィ―=ストロースのワインのお酌を見知らぬ者同士でかわす人間を観察し、ワインの交換以上の付加価値を見出した(082ページ)。恐らく、D.スロスビーの目に見えない文化資本とも還元できないか。2012/11/23
KBS
1
贈答の構造についての本。身近な習慣であるため、自分の体験と照らし合わせて考えてみると色々と発見があって楽しめる。贈り物と返礼の価値の均衡と不均衡についての部分が特に興味深く読めた。2012/06/21
kaigarayama
0
互酬性から贈答を読み解く。「無形の贈与」と「有形の返礼」のやりとりなど、モノとモノだけではない交換は確かに、と思う。あえて広いところから話を展開しているので、人類学や民俗学の知識(多少)があったほうがバックグラウンドまで理解できるかも。2011/11/14
マイケルイワン
0
10/14 完読 贈り物のバックグランドに日本人が持つ、「返礼の期待」と「返礼の義務」。互酬性と筆者はいうが、その仕組みを、ひもとく。 飛躍するが、最近の若者は大震災等でボランティアに赴く。まだまだ捨てたものではない。 究極の贈り物(ボランティア)、献血もそうだ。日本がんばれ、2011/10/14