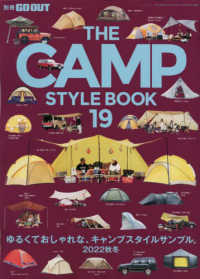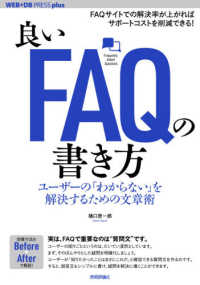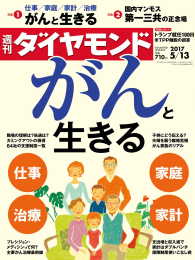内容説明
箸墓古墳の被葬者は誰か?築造時期はいつか?卑弥呼の都はどこか?文献史料・考古資料を駆使して、卑弥呼・台与の政権と邪馬台国を再検討し、初期ヤマト王権の実相を明らかにした論考。
目次
1 箸墓古墳の築造時期と被葬者―奈良県文化財調査報告書『箸墓古墳周辺の調査』を読んで(箸墓古墳の円墳先行説は成り立たない;箸墓古墳には内・外濠と周堤がある ほか)
2 箸墓古墳の被葬者をめぐって―文献史料と考古資料の扱い方について(文献史料の箸墓と卑弥呼の墓;卑弥呼の墓の「径百余歩」について ほか)
3 卑弥呼・台与の政権の成立と発展―倭国の乱と初期ヤマト政権(和辻・中山・原田の北部九州からの「東征」説;高橋・前沢の吉備からの「東征」説とその批判 ほか)
4 中国人が理解していた卑弥呼の都―中国文献の邪馬台国・女王国(九州と大和に「邪馬台」国があったとする説;伝聞としての邪馬台国にいたる日数記事 ほか)
5 卑弥呼の鬼道について―神仙思想の影響を受けた巫女王(五斗米道の「鬼道」と卑弥呼の「鬼道」;神仙思想と三角縁神獣鏡の面径 ほか)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
perLod(ピリオド)🇷🇺🇨🇳🇮🇷🇿🇦🇵🇸🇾🇪🇸🇾🇱🇧🇨🇺
5
2004年刊。著者は在野の研究家。本書は個人的に決定版となった、坂田隆『邪馬壱国の論理と数値』への批判となりうるかどうかと思い読んだ。 一、箸墓古墳の築造時期と被葬者。 「箸墓古墳=卑弥呼の墓」説への批判。卑弥呼の墓は「径百歩余」とあり、これは前方後円墳ではないとされたが、先に後円部が出来たので、それを指しているとする説が出た。しかし考古学調査では箸墓古墳は前方部と後方部が一体として造築されたとあり、要するに卑弥呼の墓ではありえない。→2024/08/28
のぶ
1
季刊誌に発表済の5本の論文をまとめた本で、順を負って古代史に入門させてくれる本にはなってません。でも、邪馬台国は「九州か近畿のどちらかにあった」という程度の単純な認識しかなかった私でも本書を通じて認識を新たにすることができました。中国側文献に残る人物(卑弥呼など)と、日本側の文献(記紀)にある人物(なんとかモモソヒメ)、その人達の埋葬をしたというそれらの文献での記述、「箸」の名称、それに現実に考古学的証拠として残る実在の古墳、それらを対応づけて同定していく過程で不確定なものが沢山あるということのようです。2014/08/27