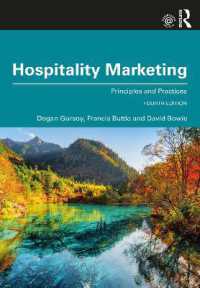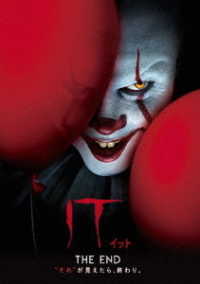内容説明
「あの炎上発言の真の深刻さ」「人生がつらい時の乗り越え方」「社会問題への対処法」…考えることは「問う」から始まる。“適切な問い”さえ立てれば、あらゆる問題に答えが出せる。変化の激しい時代を生き抜く考えるスキル。哲学対話の第一人者が丁寧に解説。
目次
第1章 問うことは、なぜ重要なのか?
第2章 そもそも、何のために問うのか?
第3章 具体的に、何を問うのか?
第4章 実際に、どのように問うのか?
第5章 どうすれば問う力がつくのか?
第6章 現実の問題にどう対処するのか?
第7章 いつ問うのをやめるべきか?
著者等紹介
梶谷真司[カジタニシンジ]
東京大学大学院総合文化研究科教授。京都大学大学院人間・環境学研究科修了。専門は哲学、医療史、比較文化。近年は学校や企業、地域コミュニティなどで「共に考える場」を作る活動を行い、いろんな人が共同で思考を作り上げていく「共創哲学」という新しいジャンルを追求している(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
hiace9000
114
『哲学』と聞くと何やら小難しく縁遠いもののように感じていたわたし(これも明らかな偏見であり思い込みだったことを、本書を読み「自らに問うて」やっと理解できた)。だが「考えることの楽しさ」、「問うことの奥深さと軽やかさ」は新発見であり、"哲学ってオモロいやん"ーなのである。答えのない問いに答えを出そうとするたゆみなき営みは、既に身の回りには嫌というほどあるし、日々それらと向き合い、問いつづけながらわたしたちは生きている。その感覚的に過ぎなかった問いを、思考的な問いとして、「問う」行為の実体を学ぶことができた。2024/08/07
アキ
102
考えることは問うことから始まる。何を問うかはその人の個性につながる。問うということは何に興味を持っているか、ひいては自分の関心領域を知ることになる、といった内容を予め予想して読んだが、まるっきり違っていた。問うことの実践と、問う力の養い方のどちらかと言うと方法論のような本であった。本書の題である「問うとはどういうことか」という問いは、本書によると、本質的な問いであり、考えるための問いということになる。問いの方法論として、一方向的と多方向的の考え方は参考になるが、それは視点の持ち方と言い換えることができる。2024/06/21
けんとまん1007
70
良い問いは、良い答え(結果)につながると、以前、読んだ本を手にして納得した。それ以来、問い、問うことを考えるようになった。まさに、問うとは哲学そのものである。問いをどのように考えるか、その意味は何かについて、いくつもの方向性が提示されている。この本自体が、問いを読者に問うているのだと思う。私見ではあるが、今は、問うこと(考えること)を厭い、答えを探すことばかりに眼が向いているのではと思う。だからこそ、問うことが大切だと改めて思う。2023/11/24
ちくわ
26
とても勉強になりました。何のために問うのか(WHY)に始まり、何を、どう、問うのか(WHAT/HOW)まで、汎用性が高い、「問い」のバイブルだと思いました。粘り強く問う最大の目的は、常識や偏見から自由になること、それにより人生の幸福度が向上すると信じます。(☆5)2024/03/28
金城 雅大(きんじょう まさひろ)
22
めちゃくちゃ良い本だった。 これはぜひ子どもにも読ませたい。2024/01/29
-

- 電子書籍
- GOLF TODAY 2024年1月号