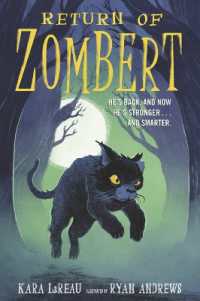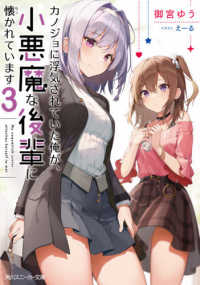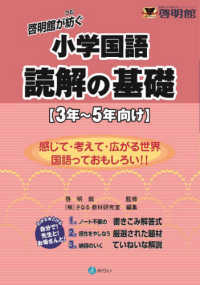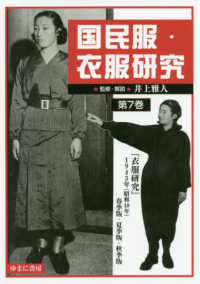出版社内容情報
有罪か無罪か?刑法はぎりぎりの攻防が繰り広げられる思考戦。ロジカルシンキングの結晶である刑法的思考で論理的思考力を養おう。
内容説明
よりよい社会はどうすればつくれるのか?法を使って問題を解決していく、論理的かつクリエイティブな“思考戦”を体験せよ!有罪か?無罪か?刑法の現場ではギリギリの思考戦が繰り広げられている。ロジカルシンキングの結晶とも言える刑法的思考で、論理的思考力を養おう!熱量たっぷり!エキサイティングな法学講座、開講!
目次
1 刑法的思考の前に:本書でやろうとしていること
2 殺人罪(刑法199条)を使って考える(「人を殺した」とはどういうことか(その1)
「人を殺した」とはどういうことか(その2) ほか)
3 身近な犯罪を使って考える(窃盗罪(刑法235条)を使って考える
名誉毀損罪(刑法230条)を使って考える ほか)
4 刑法的思考の限界とその先(刑法特有の制約;新しい犯罪は作れる ほか)
5 刑法的思考の後で:刑法について知る(日本の刑法の歴史;日本の刑法の特徴 ほか)
著者等紹介
仲道祐樹[ナカミチユウキ]
刑法学者。早稲田大学社会科学総合学術院教授。1980年大分県生まれ。大学では「刑法総論」「刑法各論」の授業を担当。刑法の基礎原理や刑罰を使うことのできる理論的な限界について研究している(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
みき
52
身近なようでいて身近ではない刑法という法律。なかなか触れる機会がないが刑法の解釈学はこう考えるんだと勉強になった。民法や憲法も初めて学んだ時も面白いなと思ったが刑法もなかなか。中身は殺人罪を例にとると、人とは何か。殺したとは何かということの意味、意義を1つづつ明らかにしていくという感じ。最終的に法益の保護という刑法の目的論に照らし合わせて有罪かが決まるという考え方が新鮮であった。でもこの考え方だと有罪無罪が前提にあって、それに併せて解釈していくとならないのかなと少し疑問です。どうなんでしょうね。2024/03/05
ま
24
刑法的思考。単なる法律のあてはめかと思いきや、他の法律を借りて解釈を試みたり、逆に新たに法律を作ったり。最適な社会をつくるための、思いの外クリエイティブな営みであった。あとがきに戦闘竜が出てきてエモい。2024/09/24
こばゆみ
9
表紙とタイトルで期待していたよりは、内容はだいぶ難しめ(^_^;)。でも筆者のあとがきを見ると、これでもかなり平易に書かれているのだなということは分かります。実際にルールを作ってみるくだりは良かったな。あとe-Govという法令の検索・閲覧システムがあることが知れて良かった(^^)2022/07/29
もけうに
4
とても面白かったが、予想以上に難しかった。表紙のポップさ・文体の平易さと、難解な内容の乖離がエグい。「刑法的思考」を教える書なので、様々な問題にすっきりした解答が与えられず、もやもや感が残る。民法と刑法の違いが面白い。民法の方が身近でわかりやすいなー。刑法はどうも難しい。諸外国との法比較も興味深い。英米法系と大陸法系。2022/09/18
TT
3
面白すぎる。今まで全く法律について学ぶ機会なかったけど、こんなにおもしろいのか。 条文は誰もが理解出来て、かつ意味の幅にゆとりがあって、そのバランスが難しさであり面白さなのかも。 色んな事例を通して、刑法の抱える課題も紹介されていてかなり考えさせられた。 1番最後には次に読むべき法律関係の本が紹介されてて親切。 高校生の時に読んでたら法学部に進学してたかも。2024/01/11