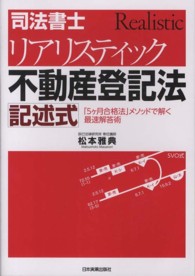出版社内容情報
経営組織の基礎理論を確立した名著。ゴードン,デール,ホールデンなどの実証的研究に対し,サイモンとともに理論的研究を展開。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
タケヒロ
11
これほど、組織を緻密に言葉だけで分析した本があっただろうか。バーナードはサイバネティクスの知識を持っていたからこれほど記述できたのだろう。そんな彼でも非論理的過程を重視しているのは驚きだった。最後に世界紛争の解決にまで協働に関して論及している事が印象的だった。めちゃくちゃ読むのにしんどかったが、後で得るものは大きいと期待したい!2016/12/24
き
7
言わずと知れた近代組織学の名著です。再読ですが、読むたびに少しずつ解ることろが増えてくる不思議な本。最初読んだ時は、まったく何を言っているのかさっぱり解らず、それでも興味のある所を何回か読むと、少し何かが解りかけてきました。頑張ってそれをもとに修士論文を書いた後、大学院の授業の課題でもう一回読むと、不思議と1回目は解らなかった所が、解るようになっています。それでも全体の半分くらいしか分からない。はじめに付録の「日常の心理」を読むと、バーナードが何を思ってこの本を書いたのか、少し理解できます。また読みます。2016/04/14
だんぶる
6
翻訳の日本語が堅苦しいが、論文だとこうなっちゃうのかもしれない。著者は、管理者の役割について組織の成り立ちからひもといて説明してくれている。そこら辺はまどろっこしいが、なんと言っても結論が熱い。人の心をつかみ協力して組織の頭数の何倍もの成果をあげる。そのために管理者はいるのだ。2015/10/17
富士さん
5
経営学の古典のはずですが、業績主義者なる人たちが本書を尊重しているとは思えないのはなぜでしょう。役割を担うことによる「誇り」を報酬で補うことはできない。「誇り」を持ちえない仕事に個人が最大の貢献をすることはない。そのため、「誇り」を提供できない集団が単なる人の集まり以上の成果を上げることはできない。特に、責任に対する物質的な対価は、「誇り」を裏打ちするための方便としてのみ重要で、対価で責任感をあがなうことはできないという指摘は、仕事というもののを健全に保つための本質がどこにあるかを見事に言い表しています。2020/04/12
yu01
4
ノーベル経済学賞をとるサイモン、コース、ウィリアムソンらがなぜバーナードを重視したかといえば、圧倒的に密度の高い全体感を持った組織の考察…とくに限定合理性と受容圏を基礎とした人間観、またソフトとハードを同時に捉える公式組織と非公式組織の相互作用…が経済学にない視点を提供したからだろう。最後の文では、協働の拡大と自由意思を持つ個人の発展、そのバランスこそが人類の福祉を向上させると信じる…それは科学ではなく宗教と哲学の問題、と言う。直接的にはファシズムへの返答だろうが、ここに経営の矜持を感じる。これが好き。2013/03/28
-

- 電子書籍
- 偽りの優等生~ボクはキミの忠実な僕(し…